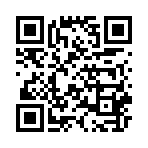2019年04月29日
10位以下?!
いーっすね!!
ブログが沢山の方に読まれるようになって。
で、ずっとeしずのランキングでは上位ランクで。
6位とか7位くらいが定位置で来たんですけど。
今日は、なんと13位!!!
もう最近は人気も無けりゃ「偽計業務妨害」にまで
遭う始末。開き直ってます。
人気なんていらねーよ、仕事くれよっ!!って。
そういう話でした。
ブログが沢山の方に読まれるようになって。
で、ずっとeしずのランキングでは上位ランクで。
6位とか7位くらいが定位置で来たんですけど。
今日は、なんと13位!!!
もう最近は人気も無けりゃ「偽計業務妨害」にまで
遭う始末。開き直ってます。
人気なんていらねーよ、仕事くれよっ!!って。
そういう話でした。
2019年04月23日
確かなこと
今日、4月23日は家内の47歳の誕生日でした。
一昨日は次女の15歳の誕生日でした。ああ忙しい。
次女は新学期になってから少し調子が掴めないで居るようです。
中学三年生になりましたから、色々と考えなければならない
事も多くなり、ストレスも多く感じるでしょう。応援したいです。
さて、最近、子供たちから「進路」について色々尋ねられたり、
相談を受ける機会が増えました。一所懸命に考えれば
考えるほど、話せば話すほどに「これで良いのか」という疑問が
私の中に湧き上がってきます。人の一生に「確かなもの」なんて
一体どれくらいあるんだという疑問です。
無責任になれません。今の私に言えることは「ただひとつ」しか
無いことに行き着きました。
それは「人は必ず死ぬ」ということだけです。確実なこと、それは
「死」です。誰でも必ず近い将来、死にます。100年も200年も
先の話ではありません。死ぬことは辛いことです。こんなにも
受け入れがたい「不幸」だけが確実に決まっているのです。
いや、不幸ではありません。確実に決まっていることですから
不幸ではありません。実に自然なことです。
家内と出会って25年。家族は一人ずつ増えていきました。
そしていつの日にか、一人ずつ減っていきます。悲しい別れが
待っています。この悲しい別れが待っていることも確実なことです。
別れが悲しいのは分かれる相手が「大切な人」だからです。
大切な人は幸せと喜びを運んできてくれます。幸せと喜びの後には
必ず悲しみがやって来る事も「確かなこと」なのです。
悲しみは実に自然なことなのです。全ての終わりが悲しみなのです。
なぜ悲しみで終わるのでしょうか。
愛が有るからです。愛が生まれるから愛の尊さを教える為に
深い悲しみという感情が与えられるのでしょう。私は、そう思います。
家内を愛しています。子供たちにも深い愛情を持っています。
家族が誕生日を迎えるたびに、いずれ訪れる耐え難い悲しみを
受け入れる日がやってくるのだと考えます。年を追うごとに愛情は
深みを増します。つまりは悲しみの深さも増すばかりなのです。
私の人生にやってきてくれた大切な家族。
感謝の言葉しか見つかりません。ありがとう。そして誕生日おめでとう。

一昨日は次女の15歳の誕生日でした。ああ忙しい。
次女は新学期になってから少し調子が掴めないで居るようです。
中学三年生になりましたから、色々と考えなければならない
事も多くなり、ストレスも多く感じるでしょう。応援したいです。
さて、最近、子供たちから「進路」について色々尋ねられたり、
相談を受ける機会が増えました。一所懸命に考えれば
考えるほど、話せば話すほどに「これで良いのか」という疑問が
私の中に湧き上がってきます。人の一生に「確かなもの」なんて
一体どれくらいあるんだという疑問です。
無責任になれません。今の私に言えることは「ただひとつ」しか
無いことに行き着きました。
それは「人は必ず死ぬ」ということだけです。確実なこと、それは
「死」です。誰でも必ず近い将来、死にます。100年も200年も
先の話ではありません。死ぬことは辛いことです。こんなにも
受け入れがたい「不幸」だけが確実に決まっているのです。
いや、不幸ではありません。確実に決まっていることですから
不幸ではありません。実に自然なことです。
家内と出会って25年。家族は一人ずつ増えていきました。
そしていつの日にか、一人ずつ減っていきます。悲しい別れが
待っています。この悲しい別れが待っていることも確実なことです。
別れが悲しいのは分かれる相手が「大切な人」だからです。
大切な人は幸せと喜びを運んできてくれます。幸せと喜びの後には
必ず悲しみがやって来る事も「確かなこと」なのです。
悲しみは実に自然なことなのです。全ての終わりが悲しみなのです。
なぜ悲しみで終わるのでしょうか。
愛が有るからです。愛が生まれるから愛の尊さを教える為に
深い悲しみという感情が与えられるのでしょう。私は、そう思います。
家内を愛しています。子供たちにも深い愛情を持っています。
家族が誕生日を迎えるたびに、いずれ訪れる耐え難い悲しみを
受け入れる日がやってくるのだと考えます。年を追うごとに愛情は
深みを増します。つまりは悲しみの深さも増すばかりなのです。
私の人生にやってきてくれた大切な家族。
感謝の言葉しか見つかりません。ありがとう。そして誕生日おめでとう。

2019年04月19日
記念日
今日、19日は私たち夫婦の結婚記念日でした。
慌しい結婚式でした。17日に入籍を済ませ、18日の早朝に軽井沢に向けて
家内と二人で軽自動車に荷物を詰め込み旅立ちました。
ウエディングドレスが物凄く大きな荷物だったのを覚えています。
スカートの部分が広がるので仕方が無いんですよね。前の日に作った
ブーケを「バケツ」に水を入れて持って行きました。良く水がこぼれなかったと
感心します。厳かな結婚式でした。幸せだった。
1ヶ月くらい前に子猫が生まれました。1匹だけ弱い猫が居ました。
次女は、ミルクを与え、なんとか自分で乳を飲み動き回れるようになるまで
介護しました。しかし最近になって風邪を引いたようでした。ウイルス性の
ものですから症状を抑える薬はあっても、風邪そのものを治すことは出来ません。
抗体が出来るのを待つしかないのです。しかし赤ちゃんです。元々弱かった
こともあって、昨日くらいから症状は深刻でした。もう3日くらい乳を飲んで
いなかったようです。子供たちは私に詳細には話しませんし、相談もして
こなかったので大して気にしていませんでした。今朝は一番で医者に連れて
行きましたが、私の見解と同様に「見守るしかない」と。また正直、長くは
無いとも言われました。私も言葉にはしませんでしたが、覚悟はありました。
それでも生きているんです。生まれたときに人口授乳で育てられたので、
大変に人に馴れています。ダンボールに入れておいても私の膝に上がってきます。
とてもとても苦しそうです。ずっと膝に乗せ、腕に抱いて家に帰ってきました。
家に着くと、すぐさま目を洗って上げて目薬を差し、鼻にお湯を入れたり、
鼻を直接吸ってあげました。ですが気道は狭くて苦しさは改善されません。
体が冷えてきたので親猫のそばに置いて毛布でくるんで上げました。
でも、苦しくて出てきてしまいます。人間を探しているようでした。寝ればよいと
思い、暫く放っておきました。鼻をすする音が小さくなったので寝たのかと思い
様子を見に行くと、もう虫の息でした。また親猫の傍に寝かせてあげました。
私は用事が有ったので、そのまま家を出ました。2時間ほどして末娘から
「死んじゃった」「もう動かない」とLINEが届きました。駄目だったか。
やはり悲しかったです。今も悲しいです。娘達の気持ちを考えると、溜まりません。
子猫は今は天国で元気に走り回っていると思います。娘には「野生の」厳しさを
教えました。生き残るということは偶然ではなく選ばれた生命力にだけ許された
試練なのだと教えました。生きるということは喜びと同時に苦難を受けるという
ことなのです。娘は「仕方ないか」と訃報を知って呟きましたが、私たちには
見えないように後部座席で泣き寝入りをしてしまいました。先程、帰宅すると
末娘が息を引き取った子猫を抱きながら泣き寝入りしていました。
先程、神楽の稽古に出掛けていきました。すると今度は次女が子猫を抱いて
横になってしまいました。しかし次女は程なくして立ち上がりました。他の子猫の
世話をするためです。変わりました。というか、成長しました。
泣いてばかりいられない。生きているものが助けを求めているんだ。今のうちにやれる
ことは、まだ有る。今やらなければならないことが有ると分かってくれたようです。
最近は酪農にも興味があるようです。生き物と一緒に暮らしたいそうです。
農業をやって酪農をやって、自分の手で育てた作物で農園カフェをやりたいんだそうです。
カフェは自分で設計するそうです。凄いバイタリティ。
「記念」それは後日に思い出として残しておくこと。娘達にも私にも今日は記念日です。
22年前に結婚式を挙げたときに頂いた結婚証明書の中にコリントの信徒への手紙の
一節が書かれていました。
信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。
その中で最も大いなるものは、愛である。
全く違うシチュエーションですが、22年前の今日も22年後の今日も、この言葉を
しっかりと噛み締めることになりました。短い一生を終えた子猫には深く感謝を
述べたいと思います。ありがとう。どうか元気で!!

慌しい結婚式でした。17日に入籍を済ませ、18日の早朝に軽井沢に向けて
家内と二人で軽自動車に荷物を詰め込み旅立ちました。
ウエディングドレスが物凄く大きな荷物だったのを覚えています。
スカートの部分が広がるので仕方が無いんですよね。前の日に作った
ブーケを「バケツ」に水を入れて持って行きました。良く水がこぼれなかったと
感心します。厳かな結婚式でした。幸せだった。
1ヶ月くらい前に子猫が生まれました。1匹だけ弱い猫が居ました。
次女は、ミルクを与え、なんとか自分で乳を飲み動き回れるようになるまで
介護しました。しかし最近になって風邪を引いたようでした。ウイルス性の
ものですから症状を抑える薬はあっても、風邪そのものを治すことは出来ません。
抗体が出来るのを待つしかないのです。しかし赤ちゃんです。元々弱かった
こともあって、昨日くらいから症状は深刻でした。もう3日くらい乳を飲んで
いなかったようです。子供たちは私に詳細には話しませんし、相談もして
こなかったので大して気にしていませんでした。今朝は一番で医者に連れて
行きましたが、私の見解と同様に「見守るしかない」と。また正直、長くは
無いとも言われました。私も言葉にはしませんでしたが、覚悟はありました。
それでも生きているんです。生まれたときに人口授乳で育てられたので、
大変に人に馴れています。ダンボールに入れておいても私の膝に上がってきます。
とてもとても苦しそうです。ずっと膝に乗せ、腕に抱いて家に帰ってきました。
家に着くと、すぐさま目を洗って上げて目薬を差し、鼻にお湯を入れたり、
鼻を直接吸ってあげました。ですが気道は狭くて苦しさは改善されません。
体が冷えてきたので親猫のそばに置いて毛布でくるんで上げました。
でも、苦しくて出てきてしまいます。人間を探しているようでした。寝ればよいと
思い、暫く放っておきました。鼻をすする音が小さくなったので寝たのかと思い
様子を見に行くと、もう虫の息でした。また親猫の傍に寝かせてあげました。
私は用事が有ったので、そのまま家を出ました。2時間ほどして末娘から
「死んじゃった」「もう動かない」とLINEが届きました。駄目だったか。
やはり悲しかったです。今も悲しいです。娘達の気持ちを考えると、溜まりません。
子猫は今は天国で元気に走り回っていると思います。娘には「野生の」厳しさを
教えました。生き残るということは偶然ではなく選ばれた生命力にだけ許された
試練なのだと教えました。生きるということは喜びと同時に苦難を受けるという
ことなのです。娘は「仕方ないか」と訃報を知って呟きましたが、私たちには
見えないように後部座席で泣き寝入りをしてしまいました。先程、帰宅すると
末娘が息を引き取った子猫を抱きながら泣き寝入りしていました。
先程、神楽の稽古に出掛けていきました。すると今度は次女が子猫を抱いて
横になってしまいました。しかし次女は程なくして立ち上がりました。他の子猫の
世話をするためです。変わりました。というか、成長しました。
泣いてばかりいられない。生きているものが助けを求めているんだ。今のうちにやれる
ことは、まだ有る。今やらなければならないことが有ると分かってくれたようです。
最近は酪農にも興味があるようです。生き物と一緒に暮らしたいそうです。
農業をやって酪農をやって、自分の手で育てた作物で農園カフェをやりたいんだそうです。
カフェは自分で設計するそうです。凄いバイタリティ。
「記念」それは後日に思い出として残しておくこと。娘達にも私にも今日は記念日です。
22年前に結婚式を挙げたときに頂いた結婚証明書の中にコリントの信徒への手紙の
一節が書かれていました。
信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。
その中で最も大いなるものは、愛である。
全く違うシチュエーションですが、22年前の今日も22年後の今日も、この言葉を
しっかりと噛み締めることになりました。短い一生を終えた子猫には深く感謝を
述べたいと思います。ありがとう。どうか元気で!!

2019年04月17日
宿題について考える 本編
さあ考えて見ましょう!
昨日は、ちょっとネットのトラブルも有って、結局解決出来ないで、
嫌になって記事を投稿しませんでした。ごめんなさい。
今日は、一昨日の記事の続きを皆さんと一緒に考えてみたいと
思います。
さて「宿題」ですが。日本人に生まれて宿題を出されたことが無い、
やったことが無いって人は「皆無」だと思います。健常者に限らず、
様々な障害を持った方でも学校に通えば「必ず」宿題を出されて、
それをやってきたと思います。知的障害があってもやらされます。
ですが、この宿題は様々な「意味合い」を持って課されています。
当然、課される側にも様々な「結果」をもたらす効果が有る訳です。
大変に広義なテーマに発展してしまいますので、今日は小学校と
中学校における宿題を中心に語ってみたいと思います。
いわゆる義務教育の現場での宿題の在り方ですね。
私は小学校と中学校とでは宿題の質というか、扱いについて、
区別するべきだと思っています。私は中学校の宿題の質について
相当に疑問を感じています。これは小学校から続くものなので、
小学校での宿題の扱いから考えていくことにしましょう。
小学校に入学すると、それまでの幼稚園や保育園との違いは「学習」
を中心とした環境になるということが最もな違いだと思います。
幼稚園や保育園でも行なわれていますが、小学校では一気に
リテラシーを高めるプログラムにシフトします。これは良く考えてみると
大変な環境変化です。保育園などでは「楽しく」「仲良く」「元気良く」
だけで生活してきたのに、突然「良い子」「頑張る子」「出来る子」に
なるためのプロットを押し付けられのです。ちょっとゾッとします。
つまり「自由」が無いのです。
だれでも6歳7歳になる年には義務教育を受けさせられます。権利と
成っていますが、まぁそれは詭弁です。子供は義務教育を受けさせ
られるのです。つまりは政府の考える「理想の日本人」になるための
プログラムを受けることになります。ただ、やはりそういった目標に
馴染めない子供も多く居ます。素直に学校の先生の言うことを聞かない、
黙って椅子に座っていられない。おしゃべりをしてしまう。喧嘩をして
しまう子。休みがちな子。宿題をやらない子。嫌だからです。
そして主張をしたいのです。また「束縛」を嫌っているからです。
早い話が小学校の1年生、それも「春」には社会からドロップアウトする
片鱗を見せている訳ですね。
学校は、そのような「アウトロー」を作り出さないために有るのです。
扱いやすく、スタンダードな「思考」や「人格」は国にとって大変に重要な
存在であり、ここに無頓着では、そもそも国家というものの体を成すことは
難しくなってしまうのです。それでも「色んな人」がいるように
思いませんか?色々な考え方を持っている人たちが、あっちこっちに
いるように見えますよね?でも「標準」ってものが歴然と存在している
ということも日本人の誰もが認めるところだとも思うのです。
いわゆる「常識」ってやつです。
常識とは考えてみれば恐ろしいものです。価値観ってものは人、様々だと
誰もが「何となく」認め合っている一方で、その個人的な価値観で生きて
行動するものを「標準」から見ると「外れている」と非難するのです。
もっと酷いのは「標準」ではなく「基準」から外れていると扱うことです。
基準とは「ひとつ」です。規定なども、その考え方に準じています。
10センチを基準とすると、その前後5ミリの長さまでは標準とし、それを
超えるものは「不良」とし、排除又は改善を要するというような考えと、
全く同じです。
義務教育のスタートでは、この「標準」が大切になってきます。長さだけの
問題ではなく「人間関係」や「命の尊厳」にまで標準的な考え方を教えます。
慎重にならざるを得ないのは「教える」だけではないことです。その考え方が、
しっかりと「身についているか」を見極める必要が「学校」には有るからです。
我々は「通信簿」という形で、その履修結果を知ることが出来ます。
ここは重要です。
教えられるということは「提示」されることです。その「教え」を見て知って、
子供たちは「自ら考えて」「個人的な感想」を持ち「個人的な考察結果」を
「所有」することが「学習」した結果だと私は思うのです。
つまり「リテラシー」そのものだと言うことです。従って、その所有した思想
について「評定」なるものは必要ないというか、相応しくないと思うのです。
そうでなければ思想を強制的に植えつけていることになりますから。
実際には、そういうことなんですが。つまり学校教育は、お題目と行動に
矛盾が有るという事なんです。こういった、なんだか薄気味の悪い事実から
目を背けないで宿題について考えてみたいと思います。
「標準」について、確かに難しいこともありますが、それでも「字」を読んだり
書いたりする、算数で計算を組み立てたり解いたりする「能力」については、
効率から言っても「体系的」な勉強方法を中心に行なわれる方が良いかも
しれません。ただ算数に関しては何となく、どうなんだろうという気持ちもあります。
小学校の低学年や中学年では「ドリル」のようなものを繰り返しやらせることで
定着を図っているのだと思います。ですが、ここが大切です。
ドリルは「つまらない」です。なぜなら「しつこい」からです。ですが、しつこく
なければドリルじゃありません。ドリルをやる意味が無いです。でも嫌だと
なるのは、しつこいからです。しつこく感じる状態とは何でしょう?
それは「もう分かったよ」って感情なのです。こんなこと分かってるから、もう
やらなくたって良いジャンってのが子供たちの考えでしょう。
ですが、大人は知っています。分かったって言ってるけど、分かってないじゃん。
ほらテストだって満点じゃないジャン!!って事です。だから正解率を上げる
為にドリル的な学習をしつこく強要します。「正解率」と書きました。
そうです、決して「満点」を目指していません。誰でも心の中で完璧は奇跡に
近いと思っているはずです。漢字は辞典に載っているもの全てが正確に書けて
読めなければ、字が存在している意味が有りません。ですが、そんな化け物、
この世に滅多にいないことは誰でも知っています。覚えきれるものではありません。
ここでも標準が出てきます。
こんな字も書けないのか?!こんな字も読めないのか?!と言われたことが
あるでしょうか?心当たりが有る方もいらっしゃるかもしれませんね。でも一体、
どれくらい字を知っていれば生活できるのでしょうか。それが小学校や中学校で
習う当用漢字+アルファくらいってことなんでしょうけど、では、それを完璧に
習得している日本人は、どれくらいいるというのでしょうか。
100個知っているよりは1000個知っている方が断然「知識」が多いです。
100個知っている子が、それでは生活に支障をきたすから150個覚えられるように
宿題を出しているのです。いいえ、違います。
この理屈は「理想」であり「当初の目的」だったのです。
今書いた記事の中にヒントはあります。そうです、学級は「ひとり」ではないのです。
30人から40人程度のクラス単位が一般的でしょう。うちの子みたいに「ひとりぼっち」
ってことも稀に有るでしょう。大勢居るクラスでは多少の偏りは有るでしょうけど、
知的障害や発達障害がなければ全然、漢字の読み書きが出来ない、計算が
出来ないという子供は、いないはずです。しかし大体同じ知識でも、テストの難易度を
上げて行けば点数の分布は広がるはずです。そうなってくると知識や能力の差は
明確になってきます。それだけ「差」が有る子供たちに、どうして同じ課題を同じ量
だけ宿題として課すのでしょうか。
私が疑問というか、問題だと思っているのは「ここ」です。
宿題の「必要量」は個人差が有るはずです。「必要量」と書きましたが、この
「必要」か、どうかについては「強制」されるべきものではないと私は思うのです。
そんなの「勝手」です。ここ重要です。
出来るようになりたい子は勝手に勉強すれば良いと短絡的に言っている訳では
ありません。まぁ本当は、そうなんですけど。これについては、もう少し後で書きます。
学習の結果については確かに量に比例する部分があります。ですが、これは
小学校の低学年や中学年までの考え方でしょう。中学校や高校になると勉強も
飛躍的に難しくなって、やってもやってもテストの結果には繋がってこないなんてこと
は普通というか常識になります。
私は小学校の校長先生と宿題の是非について話したことがあります。私は、
宿題など、下らないものを執拗に出し続けるのは非効率的であるばかりか、勉強が
嫌いに成るので止めた方が良いと言いました。すると校長先生は「それは勉強する
習慣を身につけさせているから」と「言い訳」をしました。そうです言い訳程度です(笑)
恐らく校長先生も宿題なんて必要ないなと感じていたでしょう。ですが担任の先生の
考えというか「面子」もあるので「小学校で宿題が有るのは当たり前ジャン」と
私に諦めさせたかったのでしょう。私は違うとこで諦めましたが(笑)
「目的」が大切なのです。私は自由が最も大切だと思っていますが、恣意的な
考えまで容認していません。日本人としてというよりも「人」として共通の価値観を
持つことが平和で幸福な世界を築く「基本」だと思っています。ですから義務教育で
道徳的な学習や社会生活の基盤となるような学級活動やクラスメートとの関わりを
教え導くことは重要なことだと考えています。そして日本人として「人」として、
いずれ社会に出て、我々の仲間になってゆく社会人を育てるという意味の「履修項目」
と、その履修方法について「目的」を改めて明確にするべきだと思っているのです。
それが「リテラシー」です。
リテラシーとは、テーマを理解し、それを分析して改めて表現する能力のことを言います。
決して「知識」のことでは有りません。日本人は、よく「頭が良い」という表現を使います。
知識が豊富な人にまで、この「頭が良い」という言葉を使いますが、これは間違いです。
物知りなだけで頭が言い訳ではありません。頭が良いとは正にリテラシーが高い人の
ことを言うのです。日本は先進国です。日本人の誰もが日本は優秀で能力が高いと
考えていると思います。ですが科学などのテストによるリテラシーランキングでは上位に
入りますが、読解力などでは、まだまだです。まぁそれでも世界の中ではトップクラスに
入る能力の高さです。しかし、様々なシーンでのリテラシーとなると日本は、とても上位に
ランクインできるようなリテラシーを持っているとは言えません。
それは、やはり義務教育や高等学校での授業が「覚えさせる」ことに偏重している
せいで、物事を理解し分析して、自らの考えをまとめて記し表すことが苦手なんだと
思うのです。宿題の質ですね。
目的が大事だと書きました。義務教育の目的は杓子定規なことを言わなければ、
やはり「未来を担う、未来を切り開いてくれる」日本人を育てることだと思うのです。
教養が高い人よりも、問題をあぶり出し、困難から逃げないで解決する能力のある人を
多く育てなければならないと思います。数学が役に立たないとか英語は使わないなどと
声高に言っている人は完全な失敗作です。義務教育が成功しなかった例だと思います。
誰もが高等な数学や物理を必要とするはずがありませんし、日本が占領でもされない
限りは英語も必須とは言えないかも知れませんが、それは「田舎」だけです。
今時、世界中を相手に貿易をしていない商社は明日潰れてもおかしくないです。
製造業でも同じです。農業だってそうです。学校を出て、そういった会社で働くのならば
英語は必須です。
他国のビジネスマンに日本語でない言葉で相手の意識を感じ取り、最善の
提案を自ら即時に伝えなければ成らないのです。相当な教養も必要になるでしょう。
恐らく近い将来、AIが相当に発達して多くの人材が必要とされなくなります。そうなると、
機械では出来ない仕事や「能力」を人材には求められるようになります。
人間と機械との最もな違いは「自ら」ということだと思います。それでもAIは自ら考え
意思決定する能力を持っています。AIに負けない能力を持つことは並大抵のことでは
ありません。
宿題の質の低下は「学歴偏重」が原因です。学校で行なうテストは本来の目的を
見失っています。現代では、テストは「成績」を付ける為に行なわれていると言っても
過言では有りません。そうです「ふるい」に掛ける訳です。先程も書いたようにテストの
難易度を上げれば出来、不出来が明確になります。成績が悪ければ大した高校には
進学できません。大した高校でない高校は、ろくな大学に進学できません。ろくな大学では、
ろくな就職先が有りません。大したことの無い会社では、ろくな生活が送れませんという、
妄想に近い「定説」が、いつのまにか常識になって「親」は必至に子供に勉強を強要する
ようになったのです。
そうなると、みんなが勉強が出来るようになって成績を付けにくくなります。昔のように
相対評価では、一体どこから、その点で、何が悪いんだ?とクレームが付いてしまいます。
テストの難易度を上げて「落ちこぼれ」を、わざわざ生み出します。それでも足りなくて、
今では絶対評価という「教師の主観」で成績を付けるようになってしまいました。
絶対評価は一見、ガリ勉と落ちこぼれを救うような対策に見えますが、全く効果は
無いどころか、益々子供たちから「考えるゆとり」を奪って行きました。
教師の主観で成績を付けるのです。テストが出来る云々などという前から、そもそも
宿題すらやってこない生徒に良い成績など付くはずが無いのです。だから子供たちは
必至で宿題をやります。文句があっても文句を言いません。とても辛いです。
宿題をいくらやってもテストで良い点数が取れません。当たり前です。自分に必要な勉強を
やっていないからです。親は益々心配になって学習塾に入れます。個人的に必要なことは、
ここでも教えてはくれません。っていうか、そんなこと教えられなくても個人個人なにを
すべきかなんて十分「分かって」います。なのに学校からも家庭からも能力について
低く判定され、完璧に「勉強」が嫌いになってしまいます。もうこうなると、俺は私は
「馬鹿」なんだと思い込みます。だから競争から外れて行きます。そして数学は役に立たない
とか英語は話さないとか、終いには健康で体が丈夫なら、それで良いなどと捨て台詞を
言うようになります。確かに健康が一番ですが。
目的は困難を乗り越えて未来を作る能力の開発と定着です。偏差値の高い大学に入って、
高待遇の会社に入社して、生活の安定を図る人間を「選び出す」ことではないのです。
その一部の富裕層の税収で「食わしてもらう」ことが目的でもないはずです。
何かに一所懸命に取組んで、挫折を乗り越え何度も何度も挑戦しても、その苦労や努力は
報われるとは限りません。それは人類史の常識です。しかし、だからこそ、それを継続して
いける人を育てなければならないのです。自分だけが安全に生きようなどという利己的な
考えは社会というくくりを逆手に取って、弱者を利用する封建国家と同じです。
とても世界が平和で幸福である状態には成り得ません。
最初にも言ったように小学校の低学年や中学年では基盤となる教養を体系的に身につける
方が、その後の学習には有効です。自我が芽生え、自分の考えを持てるようになる頃には
様々な疑問も生まれます。そのチャンスを利用しない手は有りません。「なぜだろう」と
思うことは出発点です。もっと分かりやすく言うと「出来ないこと」は、財産です。
出来ないことを無理に出来るようにすることは駄目なんです。育てるとは、このように
忍耐の要ることです。出来ないことを「出来るようにしたい」と思う心が人を育てます。
後に書きますと言ったのは、このことです。つまり出来るようになりたいと思わない子供に
何を「強いても」駄目なんです。もしかしたら「傍からすれば」残念な結果に終わるかも
しれませんが、そんなものは運命なのです。なにも勉強だけが全てではありません。
ですが方策はあります。一昨日「駄目教師」呼ばわりしましたが、宿題の出し方一つで、
この「子供の人格」を決めてしまう、未来を作ることが出来るかもしれないのです。
基本的に宿題は必要ないです。現代のというか、人の「本能」を利用したら良いです。
テストです。不思議なもので、どんだけ馬鹿野郎、クルクルパーでもテストの結果を気にします。
だからテストが嫌いなんです。出来る子は満点ですから気分が良いです。利用するのは
出来ない子のためです。テストを1回やれば「結果」が出ます。分かっていないこと、出来ないこと、
覚えていないことです。全く同じテストを、もう1回実施して上げるのです。その結果で
成績を付けると公言します。絶対に約束します。これは小学校の高学年や中学生に
有効な方法です。全く同じですから覚えていないことは覚えれば良いだけですし、解けない
問題は解けるようにすれば良いのです。どうやって解けるようにするかは自分で考えれば
良いです。出来たクラスメートに教えてもらえば良いです。ネットを使ったって良いです。
採点をしても「解説」をしては駄目です。自分で考えて何を、どうすれば良いか実施させます。
これが「学習」です。
別に再テストを受けるのは強制ではありません。やりたいやつだけが、やればいいです。
皆が満点を取って、何か問題が有りますか?
絶対評価ですから別に成績を付けるのにも問題はありません。自分の為に勉強をする
のですから、それは身の入りようが違います。満点を取って、若しくは最初よりも良い点を
取って、「自分の努力」が「実を結ぶ」ことを体験させてあげれば良いです。社会や理科の
学習でも応用できます。実験の結果や流れだけを覚えさせるのは役に立ちません。
社会も、つまらないノート作りなどさせないで、「なぜ」「どのようにして」を考察させて、
自力でまとめさせることが大切です。キーワードや重要人物の名前などを付け加えることで、
相手に伝わりやすいことを実感するはずです。
自分の欲で自分から能力を高めていける「環境」が大切なのです。先程、努力は報われない
と書きました。出自など、どうしようもないこともあるのが人間です。男と女でも平等とは
言えません。しかし子供たちが成長の過程で、自分が望んだ結果を手に入れることが出来る
瞬間が有ったとしたら、それは我々「大人」の努力が有ってこそ成立するのだと思うのです。
そういう環境を整えてあげることが、これからの成熟した日本の社会には必要なんだと
思うのです。「やったら出来た」。これは人を幸せにします。
先程、宿題は学習の習慣づけをするために実施していると学校の先生が言ったと書きました。
ですが私は社会に出て毎日「勉強」を欠かさずしているという人に会ったことがありません。
学習の習慣なんてものは妄想です。ただ分からないことや知らないことは聞いたり調べたり
するのは「本能」です。未開の本能であれば開花させる必要が有ります。
人は知ることに喜びを感じる本能を持っています。学校の先生には、もっともっと人を知って、
もともと備わっている能力を利用して子供を成長させていって欲しいと願います。
決して自然に逆らわないで、「豊かな時間」を失わないように子供たちが生きていけるように
尽力して欲しいと強く思うのです。
もう一度言います。
目的を明確にし、達成するための手段を考え、「委ね」、成長を待つのです。
昨日は、ちょっとネットのトラブルも有って、結局解決出来ないで、
嫌になって記事を投稿しませんでした。ごめんなさい。
今日は、一昨日の記事の続きを皆さんと一緒に考えてみたいと
思います。
さて「宿題」ですが。日本人に生まれて宿題を出されたことが無い、
やったことが無いって人は「皆無」だと思います。健常者に限らず、
様々な障害を持った方でも学校に通えば「必ず」宿題を出されて、
それをやってきたと思います。知的障害があってもやらされます。
ですが、この宿題は様々な「意味合い」を持って課されています。
当然、課される側にも様々な「結果」をもたらす効果が有る訳です。
大変に広義なテーマに発展してしまいますので、今日は小学校と
中学校における宿題を中心に語ってみたいと思います。
いわゆる義務教育の現場での宿題の在り方ですね。
私は小学校と中学校とでは宿題の質というか、扱いについて、
区別するべきだと思っています。私は中学校の宿題の質について
相当に疑問を感じています。これは小学校から続くものなので、
小学校での宿題の扱いから考えていくことにしましょう。
小学校に入学すると、それまでの幼稚園や保育園との違いは「学習」
を中心とした環境になるということが最もな違いだと思います。
幼稚園や保育園でも行なわれていますが、小学校では一気に
リテラシーを高めるプログラムにシフトします。これは良く考えてみると
大変な環境変化です。保育園などでは「楽しく」「仲良く」「元気良く」
だけで生活してきたのに、突然「良い子」「頑張る子」「出来る子」に
なるためのプロットを押し付けられのです。ちょっとゾッとします。
つまり「自由」が無いのです。
だれでも6歳7歳になる年には義務教育を受けさせられます。権利と
成っていますが、まぁそれは詭弁です。子供は義務教育を受けさせ
られるのです。つまりは政府の考える「理想の日本人」になるための
プログラムを受けることになります。ただ、やはりそういった目標に
馴染めない子供も多く居ます。素直に学校の先生の言うことを聞かない、
黙って椅子に座っていられない。おしゃべりをしてしまう。喧嘩をして
しまう子。休みがちな子。宿題をやらない子。嫌だからです。
そして主張をしたいのです。また「束縛」を嫌っているからです。
早い話が小学校の1年生、それも「春」には社会からドロップアウトする
片鱗を見せている訳ですね。
学校は、そのような「アウトロー」を作り出さないために有るのです。
扱いやすく、スタンダードな「思考」や「人格」は国にとって大変に重要な
存在であり、ここに無頓着では、そもそも国家というものの体を成すことは
難しくなってしまうのです。それでも「色んな人」がいるように
思いませんか?色々な考え方を持っている人たちが、あっちこっちに
いるように見えますよね?でも「標準」ってものが歴然と存在している
ということも日本人の誰もが認めるところだとも思うのです。
いわゆる「常識」ってやつです。
常識とは考えてみれば恐ろしいものです。価値観ってものは人、様々だと
誰もが「何となく」認め合っている一方で、その個人的な価値観で生きて
行動するものを「標準」から見ると「外れている」と非難するのです。
もっと酷いのは「標準」ではなく「基準」から外れていると扱うことです。
基準とは「ひとつ」です。規定なども、その考え方に準じています。
10センチを基準とすると、その前後5ミリの長さまでは標準とし、それを
超えるものは「不良」とし、排除又は改善を要するというような考えと、
全く同じです。
義務教育のスタートでは、この「標準」が大切になってきます。長さだけの
問題ではなく「人間関係」や「命の尊厳」にまで標準的な考え方を教えます。
慎重にならざるを得ないのは「教える」だけではないことです。その考え方が、
しっかりと「身についているか」を見極める必要が「学校」には有るからです。
我々は「通信簿」という形で、その履修結果を知ることが出来ます。
ここは重要です。
教えられるということは「提示」されることです。その「教え」を見て知って、
子供たちは「自ら考えて」「個人的な感想」を持ち「個人的な考察結果」を
「所有」することが「学習」した結果だと私は思うのです。
つまり「リテラシー」そのものだと言うことです。従って、その所有した思想
について「評定」なるものは必要ないというか、相応しくないと思うのです。
そうでなければ思想を強制的に植えつけていることになりますから。
実際には、そういうことなんですが。つまり学校教育は、お題目と行動に
矛盾が有るという事なんです。こういった、なんだか薄気味の悪い事実から
目を背けないで宿題について考えてみたいと思います。
「標準」について、確かに難しいこともありますが、それでも「字」を読んだり
書いたりする、算数で計算を組み立てたり解いたりする「能力」については、
効率から言っても「体系的」な勉強方法を中心に行なわれる方が良いかも
しれません。ただ算数に関しては何となく、どうなんだろうという気持ちもあります。
小学校の低学年や中学年では「ドリル」のようなものを繰り返しやらせることで
定着を図っているのだと思います。ですが、ここが大切です。
ドリルは「つまらない」です。なぜなら「しつこい」からです。ですが、しつこく
なければドリルじゃありません。ドリルをやる意味が無いです。でも嫌だと
なるのは、しつこいからです。しつこく感じる状態とは何でしょう?
それは「もう分かったよ」って感情なのです。こんなこと分かってるから、もう
やらなくたって良いジャンってのが子供たちの考えでしょう。
ですが、大人は知っています。分かったって言ってるけど、分かってないじゃん。
ほらテストだって満点じゃないジャン!!って事です。だから正解率を上げる
為にドリル的な学習をしつこく強要します。「正解率」と書きました。
そうです、決して「満点」を目指していません。誰でも心の中で完璧は奇跡に
近いと思っているはずです。漢字は辞典に載っているもの全てが正確に書けて
読めなければ、字が存在している意味が有りません。ですが、そんな化け物、
この世に滅多にいないことは誰でも知っています。覚えきれるものではありません。
ここでも標準が出てきます。
こんな字も書けないのか?!こんな字も読めないのか?!と言われたことが
あるでしょうか?心当たりが有る方もいらっしゃるかもしれませんね。でも一体、
どれくらい字を知っていれば生活できるのでしょうか。それが小学校や中学校で
習う当用漢字+アルファくらいってことなんでしょうけど、では、それを完璧に
習得している日本人は、どれくらいいるというのでしょうか。
100個知っているよりは1000個知っている方が断然「知識」が多いです。
100個知っている子が、それでは生活に支障をきたすから150個覚えられるように
宿題を出しているのです。いいえ、違います。
この理屈は「理想」であり「当初の目的」だったのです。
今書いた記事の中にヒントはあります。そうです、学級は「ひとり」ではないのです。
30人から40人程度のクラス単位が一般的でしょう。うちの子みたいに「ひとりぼっち」
ってことも稀に有るでしょう。大勢居るクラスでは多少の偏りは有るでしょうけど、
知的障害や発達障害がなければ全然、漢字の読み書きが出来ない、計算が
出来ないという子供は、いないはずです。しかし大体同じ知識でも、テストの難易度を
上げて行けば点数の分布は広がるはずです。そうなってくると知識や能力の差は
明確になってきます。それだけ「差」が有る子供たちに、どうして同じ課題を同じ量
だけ宿題として課すのでしょうか。
私が疑問というか、問題だと思っているのは「ここ」です。
宿題の「必要量」は個人差が有るはずです。「必要量」と書きましたが、この
「必要」か、どうかについては「強制」されるべきものではないと私は思うのです。
そんなの「勝手」です。ここ重要です。
出来るようになりたい子は勝手に勉強すれば良いと短絡的に言っている訳では
ありません。まぁ本当は、そうなんですけど。これについては、もう少し後で書きます。
学習の結果については確かに量に比例する部分があります。ですが、これは
小学校の低学年や中学年までの考え方でしょう。中学校や高校になると勉強も
飛躍的に難しくなって、やってもやってもテストの結果には繋がってこないなんてこと
は普通というか常識になります。
私は小学校の校長先生と宿題の是非について話したことがあります。私は、
宿題など、下らないものを執拗に出し続けるのは非効率的であるばかりか、勉強が
嫌いに成るので止めた方が良いと言いました。すると校長先生は「それは勉強する
習慣を身につけさせているから」と「言い訳」をしました。そうです言い訳程度です(笑)
恐らく校長先生も宿題なんて必要ないなと感じていたでしょう。ですが担任の先生の
考えというか「面子」もあるので「小学校で宿題が有るのは当たり前ジャン」と
私に諦めさせたかったのでしょう。私は違うとこで諦めましたが(笑)
「目的」が大切なのです。私は自由が最も大切だと思っていますが、恣意的な
考えまで容認していません。日本人としてというよりも「人」として共通の価値観を
持つことが平和で幸福な世界を築く「基本」だと思っています。ですから義務教育で
道徳的な学習や社会生活の基盤となるような学級活動やクラスメートとの関わりを
教え導くことは重要なことだと考えています。そして日本人として「人」として、
いずれ社会に出て、我々の仲間になってゆく社会人を育てるという意味の「履修項目」
と、その履修方法について「目的」を改めて明確にするべきだと思っているのです。
それが「リテラシー」です。
リテラシーとは、テーマを理解し、それを分析して改めて表現する能力のことを言います。
決して「知識」のことでは有りません。日本人は、よく「頭が良い」という表現を使います。
知識が豊富な人にまで、この「頭が良い」という言葉を使いますが、これは間違いです。
物知りなだけで頭が言い訳ではありません。頭が良いとは正にリテラシーが高い人の
ことを言うのです。日本は先進国です。日本人の誰もが日本は優秀で能力が高いと
考えていると思います。ですが科学などのテストによるリテラシーランキングでは上位に
入りますが、読解力などでは、まだまだです。まぁそれでも世界の中ではトップクラスに
入る能力の高さです。しかし、様々なシーンでのリテラシーとなると日本は、とても上位に
ランクインできるようなリテラシーを持っているとは言えません。
それは、やはり義務教育や高等学校での授業が「覚えさせる」ことに偏重している
せいで、物事を理解し分析して、自らの考えをまとめて記し表すことが苦手なんだと
思うのです。宿題の質ですね。
目的が大事だと書きました。義務教育の目的は杓子定規なことを言わなければ、
やはり「未来を担う、未来を切り開いてくれる」日本人を育てることだと思うのです。
教養が高い人よりも、問題をあぶり出し、困難から逃げないで解決する能力のある人を
多く育てなければならないと思います。数学が役に立たないとか英語は使わないなどと
声高に言っている人は完全な失敗作です。義務教育が成功しなかった例だと思います。
誰もが高等な数学や物理を必要とするはずがありませんし、日本が占領でもされない
限りは英語も必須とは言えないかも知れませんが、それは「田舎」だけです。
今時、世界中を相手に貿易をしていない商社は明日潰れてもおかしくないです。
製造業でも同じです。農業だってそうです。学校を出て、そういった会社で働くのならば
英語は必須です。
他国のビジネスマンに日本語でない言葉で相手の意識を感じ取り、最善の
提案を自ら即時に伝えなければ成らないのです。相当な教養も必要になるでしょう。
恐らく近い将来、AIが相当に発達して多くの人材が必要とされなくなります。そうなると、
機械では出来ない仕事や「能力」を人材には求められるようになります。
人間と機械との最もな違いは「自ら」ということだと思います。それでもAIは自ら考え
意思決定する能力を持っています。AIに負けない能力を持つことは並大抵のことでは
ありません。
宿題の質の低下は「学歴偏重」が原因です。学校で行なうテストは本来の目的を
見失っています。現代では、テストは「成績」を付ける為に行なわれていると言っても
過言では有りません。そうです「ふるい」に掛ける訳です。先程も書いたようにテストの
難易度を上げれば出来、不出来が明確になります。成績が悪ければ大した高校には
進学できません。大した高校でない高校は、ろくな大学に進学できません。ろくな大学では、
ろくな就職先が有りません。大したことの無い会社では、ろくな生活が送れませんという、
妄想に近い「定説」が、いつのまにか常識になって「親」は必至に子供に勉強を強要する
ようになったのです。
そうなると、みんなが勉強が出来るようになって成績を付けにくくなります。昔のように
相対評価では、一体どこから、その点で、何が悪いんだ?とクレームが付いてしまいます。
テストの難易度を上げて「落ちこぼれ」を、わざわざ生み出します。それでも足りなくて、
今では絶対評価という「教師の主観」で成績を付けるようになってしまいました。
絶対評価は一見、ガリ勉と落ちこぼれを救うような対策に見えますが、全く効果は
無いどころか、益々子供たちから「考えるゆとり」を奪って行きました。
教師の主観で成績を付けるのです。テストが出来る云々などという前から、そもそも
宿題すらやってこない生徒に良い成績など付くはずが無いのです。だから子供たちは
必至で宿題をやります。文句があっても文句を言いません。とても辛いです。
宿題をいくらやってもテストで良い点数が取れません。当たり前です。自分に必要な勉強を
やっていないからです。親は益々心配になって学習塾に入れます。個人的に必要なことは、
ここでも教えてはくれません。っていうか、そんなこと教えられなくても個人個人なにを
すべきかなんて十分「分かって」います。なのに学校からも家庭からも能力について
低く判定され、完璧に「勉強」が嫌いになってしまいます。もうこうなると、俺は私は
「馬鹿」なんだと思い込みます。だから競争から外れて行きます。そして数学は役に立たない
とか英語は話さないとか、終いには健康で体が丈夫なら、それで良いなどと捨て台詞を
言うようになります。確かに健康が一番ですが。
目的は困難を乗り越えて未来を作る能力の開発と定着です。偏差値の高い大学に入って、
高待遇の会社に入社して、生活の安定を図る人間を「選び出す」ことではないのです。
その一部の富裕層の税収で「食わしてもらう」ことが目的でもないはずです。
何かに一所懸命に取組んで、挫折を乗り越え何度も何度も挑戦しても、その苦労や努力は
報われるとは限りません。それは人類史の常識です。しかし、だからこそ、それを継続して
いける人を育てなければならないのです。自分だけが安全に生きようなどという利己的な
考えは社会というくくりを逆手に取って、弱者を利用する封建国家と同じです。
とても世界が平和で幸福である状態には成り得ません。
最初にも言ったように小学校の低学年や中学年では基盤となる教養を体系的に身につける
方が、その後の学習には有効です。自我が芽生え、自分の考えを持てるようになる頃には
様々な疑問も生まれます。そのチャンスを利用しない手は有りません。「なぜだろう」と
思うことは出発点です。もっと分かりやすく言うと「出来ないこと」は、財産です。
出来ないことを無理に出来るようにすることは駄目なんです。育てるとは、このように
忍耐の要ることです。出来ないことを「出来るようにしたい」と思う心が人を育てます。
後に書きますと言ったのは、このことです。つまり出来るようになりたいと思わない子供に
何を「強いても」駄目なんです。もしかしたら「傍からすれば」残念な結果に終わるかも
しれませんが、そんなものは運命なのです。なにも勉強だけが全てではありません。
ですが方策はあります。一昨日「駄目教師」呼ばわりしましたが、宿題の出し方一つで、
この「子供の人格」を決めてしまう、未来を作ることが出来るかもしれないのです。
基本的に宿題は必要ないです。現代のというか、人の「本能」を利用したら良いです。
テストです。不思議なもので、どんだけ馬鹿野郎、クルクルパーでもテストの結果を気にします。
だからテストが嫌いなんです。出来る子は満点ですから気分が良いです。利用するのは
出来ない子のためです。テストを1回やれば「結果」が出ます。分かっていないこと、出来ないこと、
覚えていないことです。全く同じテストを、もう1回実施して上げるのです。その結果で
成績を付けると公言します。絶対に約束します。これは小学校の高学年や中学生に
有効な方法です。全く同じですから覚えていないことは覚えれば良いだけですし、解けない
問題は解けるようにすれば良いのです。どうやって解けるようにするかは自分で考えれば
良いです。出来たクラスメートに教えてもらえば良いです。ネットを使ったって良いです。
採点をしても「解説」をしては駄目です。自分で考えて何を、どうすれば良いか実施させます。
これが「学習」です。
別に再テストを受けるのは強制ではありません。やりたいやつだけが、やればいいです。
皆が満点を取って、何か問題が有りますか?
絶対評価ですから別に成績を付けるのにも問題はありません。自分の為に勉強をする
のですから、それは身の入りようが違います。満点を取って、若しくは最初よりも良い点を
取って、「自分の努力」が「実を結ぶ」ことを体験させてあげれば良いです。社会や理科の
学習でも応用できます。実験の結果や流れだけを覚えさせるのは役に立ちません。
社会も、つまらないノート作りなどさせないで、「なぜ」「どのようにして」を考察させて、
自力でまとめさせることが大切です。キーワードや重要人物の名前などを付け加えることで、
相手に伝わりやすいことを実感するはずです。
自分の欲で自分から能力を高めていける「環境」が大切なのです。先程、努力は報われない
と書きました。出自など、どうしようもないこともあるのが人間です。男と女でも平等とは
言えません。しかし子供たちが成長の過程で、自分が望んだ結果を手に入れることが出来る
瞬間が有ったとしたら、それは我々「大人」の努力が有ってこそ成立するのだと思うのです。
そういう環境を整えてあげることが、これからの成熟した日本の社会には必要なんだと
思うのです。「やったら出来た」。これは人を幸せにします。
先程、宿題は学習の習慣づけをするために実施していると学校の先生が言ったと書きました。
ですが私は社会に出て毎日「勉強」を欠かさずしているという人に会ったことがありません。
学習の習慣なんてものは妄想です。ただ分からないことや知らないことは聞いたり調べたり
するのは「本能」です。未開の本能であれば開花させる必要が有ります。
人は知ることに喜びを感じる本能を持っています。学校の先生には、もっともっと人を知って、
もともと備わっている能力を利用して子供を成長させていって欲しいと願います。
決して自然に逆らわないで、「豊かな時間」を失わないように子供たちが生きていけるように
尽力して欲しいと強く思うのです。
もう一度言います。
目的を明確にし、達成するための手段を考え、「委ね」、成長を待つのです。
2019年04月15日
宿題について物凄く考える。定期的に。
物凄く言いたくなりました。
毎年、春に書いているかもしれません。
長期の休みにも書いているかもしれません。
宿題、反対派の私としては、こいつを考える
度に教員の無能さというか、しっかりしろよ!
お前ら公僕じゃねーだろ?!と怒り心頭モードに
なってしまうんです。
詳細は明日にでも語りますかね。
もしかして、この記事に辿り着いた新人先生の
「今後の30年」の教師人生に大きな影響を
与えるかもしれませんので、一生懸命に
語りたい所存にございます。
毎年、春に書いているかもしれません。
長期の休みにも書いているかもしれません。
宿題、反対派の私としては、こいつを考える
度に教員の無能さというか、しっかりしろよ!
お前ら公僕じゃねーだろ?!と怒り心頭モードに
なってしまうんです。
詳細は明日にでも語りますかね。
もしかして、この記事に辿り着いた新人先生の
「今後の30年」の教師人生に大きな影響を
与えるかもしれませんので、一生懸命に
語りたい所存にございます。
2019年04月14日
タラノメ
朝一番で友人が採れたてのタラノメを届けてくれた。
昨夜は遅くまで晩酌をしたのと、ここのところの
疲労がピークに達していたせいで、随分と寝坊を
してしまって。偏頭痛も止まないで辛い毎日を
送っている次第です。
友人は、三女にトゲトゲの薔薇のような「葉っぱ」を
そっと手渡してくれた。「パパにやってくれ」と
託してくれたのだ。会えなかった。
今年の春は遅い。全く微睡むような陽気を感じられない。
それでも。
こうして春の味覚を味わうと季節は確実に
移っているのだと知ることができる。
ここの所の数年は、決まって友人が春を教えて
くれる。手で掴むのに難儀するということは、
採るには、もっと難儀する。
「おい今年も採れたぞ」そう言って心も一緒に
届けてくれる。有り難いことだ。
天ぷらを食いながら、春一番のシャルドネを飲む。
昨夜は遅くまで晩酌をしたのと、ここのところの
疲労がピークに達していたせいで、随分と寝坊を
してしまって。偏頭痛も止まないで辛い毎日を
送っている次第です。
友人は、三女にトゲトゲの薔薇のような「葉っぱ」を
そっと手渡してくれた。「パパにやってくれ」と
託してくれたのだ。会えなかった。
今年の春は遅い。全く微睡むような陽気を感じられない。
それでも。
こうして春の味覚を味わうと季節は確実に
移っているのだと知ることができる。
ここの所の数年は、決まって友人が春を教えて
くれる。手で掴むのに難儀するということは、
採るには、もっと難儀する。
「おい今年も採れたぞ」そう言って心も一緒に
届けてくれる。有り難いことだ。
天ぷらを食いながら、春一番のシャルドネを飲む。
2019年04月13日
毎日の料理
最近、変わったなぁ~ってシミジミ思うことがあります。
私は「9人家族」のコックでした。家内は殆ど台所に立つ事は
無いので、子供の弁当作りから、毎日の夕飯の支度は
私の仕事です。どうかすれば家内の弁当まで作っていますから、
一日のうちで「飯の支度」に掛ける時間は相当なものです。
毎日スーパーで買い物する時間も有りますからね。最近までは
長男が家に居ましたから、必然的に長男の朝飯兼昼飯を
作らねば成らず、大変な頻度で家内の分も作っているのです。
まぁ私は「ご飯」的なものは終日食べませんので、8人分を
作るという感覚なんですが。それでも自分の酒の肴は元より、
家内の晩酌の肴まで作りますから、もう自分が飲む頃には、
ヘトヘトなんでございます。それでも40代の半ば頃、いや、
つい最近まで、飯を作り終えてからでも締め切りの迫った設計を
深夜、明け方までやっていましたね。
最近では、初老の気配も感じるようになり、もう全く無理が
利かなくなってきました。どうかすれば疲れきってしまって、
風呂も週に2度程度しか入らないなんて事が頻繁にあります。
うう疲れた...
肩も凝りまくって...最近では子供が肩揉みをしてくれるなんて
ことも限りなくゼロになりました。家内にも揉んでもらえなくなり
ましたが、そこは、やはり稼ぎに比例するのだと諦めておりまし
たが、最近は余りに私が気の毒に見えたのか、それとも哀れ
んでかは分かりませんが長時間マッサージをしてくれることも
あります。生きてて良かった。
長男が居たときには「誰か肩揉んで」と私が叫んでも家族全員が
無視をしていると必ずやってきて慣れない手つきで一生懸命に
肩を揉んでくれました。
さて話は逸れましたが。変わったのは料理に掛かる時間です。
「掛ける」時間ではなくて「掛かる」時間です。今日の夕飯は、
娘達の大好きな「オムライス」でした。スープストックから作って
置くと手早く作れます。スープの中に玉ねぎも鶏肉も入れて
おきます。それに「三人分」くらいずつご飯を入れて、チキンライス
を作っておきます。卵に包むには1人前ずつしか出来ませんから、
これを最低でも7回繰り返すわけですね。しんど(T-T)
我が家のコンロは業務用ですが、それでも炒め物は3人前が
限界で、美味しく作るには2人前ずつが理想なんです。
野菜炒めのように水が出やすいものは2人前で作ります。
ってことは4回作れば家内の分まで出来上がるんですね。
自分の分まで作る気力が残っていないので私は基本的に
「毎日」刺身だけを食います。亀かっ?!って感じですね。切るだけ
で、あとは醤油をつけて食うだけですから、疲れきった初老の
親父には丁度良い肴です。
毎日、買い物に行くときも未だに出て行った「息子達」のことを
考えてしまいます。あいつ、これ好きだからとか、今日は肉を
食わせようかなとか、いなくなってしまったのに、最初に頭に
思い浮かべるのは息子達のことです。
ちゃんと食ってるのかな。毎日考えます。大した用も無いのに
毎日電話やLINEをします。家内も「何食べた?」と必ず聞いて
います。お金の使い方を知らないので、恐々と使っているようです。
無くなったらどうしよう。それですね。最初の1週間は引越しの
時に買って上げたレトルトなんかを中心に食べていたようです。
怖くて1日1食しか食べていなかったようです。泣けました。
最近では昼飯は学食を利用して夕飯は野菜も取るように心がけて
自分で作ったり、外で食べているようです。「一人居酒屋」も
経験したようです。生ビールと焼き鳥が映っている画像を送って
きてくれました。もうじき22歳です。なんか嬉しいような寂しいような。
段々増えてきたから出来ていたんだ思います。長男には22年間
毎日、飯を作ってきたんだと思い出しています。ミルクもあげました。
離乳食も売っている物は、ほんの少しだけしか使わないで、
色々工夫して作って食べさせていましたね。懐かしい。
先程6人分のオムライスを作り終えて、丁度「2人分」のスープが
残ってしまいました。まだ「感」が8人分になっています。
寂しいですね。
今朝、次男からLINEで風邪薬を洋服と一緒に送ってくれと
届きました。家内は宅急便屋で息子に電話をしたときに久々に聞く
声に泣いてしまいそうだったと言いました。それを聞いた私も
泣きたくなりました。
いずれ、家内と二人分だけの食卓になります。今は想像すらしたく
ありません。どこでもドアが有ったら今すぐにオムライスを届けたいです。

私は「9人家族」のコックでした。家内は殆ど台所に立つ事は
無いので、子供の弁当作りから、毎日の夕飯の支度は
私の仕事です。どうかすれば家内の弁当まで作っていますから、
一日のうちで「飯の支度」に掛ける時間は相当なものです。
毎日スーパーで買い物する時間も有りますからね。最近までは
長男が家に居ましたから、必然的に長男の朝飯兼昼飯を
作らねば成らず、大変な頻度で家内の分も作っているのです。
まぁ私は「ご飯」的なものは終日食べませんので、8人分を
作るという感覚なんですが。それでも自分の酒の肴は元より、
家内の晩酌の肴まで作りますから、もう自分が飲む頃には、
ヘトヘトなんでございます。それでも40代の半ば頃、いや、
つい最近まで、飯を作り終えてからでも締め切りの迫った設計を
深夜、明け方までやっていましたね。
最近では、初老の気配も感じるようになり、もう全く無理が
利かなくなってきました。どうかすれば疲れきってしまって、
風呂も週に2度程度しか入らないなんて事が頻繁にあります。
うう疲れた...
肩も凝りまくって...最近では子供が肩揉みをしてくれるなんて
ことも限りなくゼロになりました。家内にも揉んでもらえなくなり
ましたが、そこは、やはり稼ぎに比例するのだと諦めておりまし
たが、最近は余りに私が気の毒に見えたのか、それとも哀れ
んでかは分かりませんが長時間マッサージをしてくれることも
あります。生きてて良かった。
長男が居たときには「誰か肩揉んで」と私が叫んでも家族全員が
無視をしていると必ずやってきて慣れない手つきで一生懸命に
肩を揉んでくれました。
さて話は逸れましたが。変わったのは料理に掛かる時間です。
「掛ける」時間ではなくて「掛かる」時間です。今日の夕飯は、
娘達の大好きな「オムライス」でした。スープストックから作って
置くと手早く作れます。スープの中に玉ねぎも鶏肉も入れて
おきます。それに「三人分」くらいずつご飯を入れて、チキンライス
を作っておきます。卵に包むには1人前ずつしか出来ませんから、
これを最低でも7回繰り返すわけですね。しんど(T-T)
我が家のコンロは業務用ですが、それでも炒め物は3人前が
限界で、美味しく作るには2人前ずつが理想なんです。
野菜炒めのように水が出やすいものは2人前で作ります。
ってことは4回作れば家内の分まで出来上がるんですね。
自分の分まで作る気力が残っていないので私は基本的に
「毎日」刺身だけを食います。亀かっ?!って感じですね。切るだけ
で、あとは醤油をつけて食うだけですから、疲れきった初老の
親父には丁度良い肴です。
毎日、買い物に行くときも未だに出て行った「息子達」のことを
考えてしまいます。あいつ、これ好きだからとか、今日は肉を
食わせようかなとか、いなくなってしまったのに、最初に頭に
思い浮かべるのは息子達のことです。
ちゃんと食ってるのかな。毎日考えます。大した用も無いのに
毎日電話やLINEをします。家内も「何食べた?」と必ず聞いて
います。お金の使い方を知らないので、恐々と使っているようです。
無くなったらどうしよう。それですね。最初の1週間は引越しの
時に買って上げたレトルトなんかを中心に食べていたようです。
怖くて1日1食しか食べていなかったようです。泣けました。
最近では昼飯は学食を利用して夕飯は野菜も取るように心がけて
自分で作ったり、外で食べているようです。「一人居酒屋」も
経験したようです。生ビールと焼き鳥が映っている画像を送って
きてくれました。もうじき22歳です。なんか嬉しいような寂しいような。
段々増えてきたから出来ていたんだ思います。長男には22年間
毎日、飯を作ってきたんだと思い出しています。ミルクもあげました。
離乳食も売っている物は、ほんの少しだけしか使わないで、
色々工夫して作って食べさせていましたね。懐かしい。
先程6人分のオムライスを作り終えて、丁度「2人分」のスープが
残ってしまいました。まだ「感」が8人分になっています。
寂しいですね。
今朝、次男からLINEで風邪薬を洋服と一緒に送ってくれと
届きました。家内は宅急便屋で息子に電話をしたときに久々に聞く
声に泣いてしまいそうだったと言いました。それを聞いた私も
泣きたくなりました。
いずれ、家内と二人分だけの食卓になります。今は想像すらしたく
ありません。どこでもドアが有ったら今すぐにオムライスを届けたいです。

2019年04月12日
奨学金申請
今、大わらわじゃないでしょうか。
大学に入学すると直ぐにガイダンスがありますね。
でも親御さんも学生さんも気になるのは「奨学金」じゃないでしょうか。
幸運にも「給付型」の奨学金、つまり「借金」をしないでも進学できた
方には関係の無い話なんですが。実際のところ2.6人に1人くらいが
貸与型の奨学金を利用しているらしい。二人に一人だと思っておけば
近い線だろう。
ってことで、恐らく授業の内容なんかより、ちゃんと手続きが出来るのか、
出来たのかってのが一番感心が有るっていうか、心配事なんだろう。
で、また沢山の書類なんかを揃えなければならない。親は大変だ。
大変なのは「家を出た」子供を持った世帯だ。イチイチ書類を子供に
送って上げなければ成らない。面倒は、さておいても「時間」が、
タイトだ。説明されると大して時間もおかないで、さっさと提出するように
と学校に言われる。で、分からないことを聞こうにも事務員の対応は
「冷たい」なんてことが往々にして有る。
高校に在学中に「予約採用」されていれば比較的、あくまで比較的だが、
容易に申請が進められるが、多浪人生などの場合には入学後「自分で」
手続きを行なわなければならない。これが厄介だ。子供には難しい、
生まれて初めて聞くような「語句」ばかり。長い説明書も難解だ。
新入生は、やらなければならないことも多く有るのに、この申請は結構な
ストレスになっているだろう。ご他聞に漏れず我が家も辟易なうだ。
まぁこれが済めば新生活を満喫できると思って、頑張るしかないのだ。
ああ...そうなんだ...
大学に入学すると直ぐにガイダンスがありますね。
でも親御さんも学生さんも気になるのは「奨学金」じゃないでしょうか。
幸運にも「給付型」の奨学金、つまり「借金」をしないでも進学できた
方には関係の無い話なんですが。実際のところ2.6人に1人くらいが
貸与型の奨学金を利用しているらしい。二人に一人だと思っておけば
近い線だろう。
ってことで、恐らく授業の内容なんかより、ちゃんと手続きが出来るのか、
出来たのかってのが一番感心が有るっていうか、心配事なんだろう。
で、また沢山の書類なんかを揃えなければならない。親は大変だ。
大変なのは「家を出た」子供を持った世帯だ。イチイチ書類を子供に
送って上げなければ成らない。面倒は、さておいても「時間」が、
タイトだ。説明されると大して時間もおかないで、さっさと提出するように
と学校に言われる。で、分からないことを聞こうにも事務員の対応は
「冷たい」なんてことが往々にして有る。
高校に在学中に「予約採用」されていれば比較的、あくまで比較的だが、
容易に申請が進められるが、多浪人生などの場合には入学後「自分で」
手続きを行なわなければならない。これが厄介だ。子供には難しい、
生まれて初めて聞くような「語句」ばかり。長い説明書も難解だ。
新入生は、やらなければならないことも多く有るのに、この申請は結構な
ストレスになっているだろう。ご他聞に漏れず我が家も辟易なうだ。
まぁこれが済めば新生活を満喫できると思って、頑張るしかないのだ。
ああ...そうなんだ...
2019年04月08日
成長 変化
今日は長男の入学式です。
6年前の同じ日に高校の入学式を迎えました。あっという間です。
ですが振り返ると随分と色々有った6年間でもあります。
先週の土曜日に次男と三男も入学式を済ませました。
次男は東京に暮らすことになりましたが三男は自宅から通学する
ことになりました。
三男は小学校の5、6年生くらいから扱いにくくなりました。
中学に入ると顕著になった反抗的な態度。でも反抗とは違うような、
なんとも掴みどころのない不思議な世界を貫いていました。
反抗期ではないんです。
三男は我が家では一番発達障害が顕著な子供です。小さな頃から
「頑な」な正確で口数も少なかったです。余りにも、しゃべりださない
ので知的障害が有るのかもしれないと本気で心配していました。
最近になって発達障害やアスペルガー症候群のことを知ったので、
今までの様々な受け入れがたい不思議な経験を理解し、親として
受け入れられるようになりました。でも、受け入れられると言っても、
その特異な性質というか感情表現は相当に親には堪えるものでして、
一体どうすれば、まともな親子関係が築けるのかと悩みに悩み、
一人で泣いているときも随分と有りました。っていうか進行形です。
三男は公立大学の受験に失敗しました。地元の私立大学に通う
ことになりましたが、当初は浮かない表情でした。絶対に言葉には
しませんし、感情も表には出しません。それでも18年も一緒に暮らし
ていると、息子が何を考えているのか薄っすらとは分かるものです。
浮かない理由は勿論、第一志望に受からなかったことでしょう。
そして長男と次男は家を出て行くのに自分は家に残るということが
決定したからだと私は受け取っていました。
これは非常に複雑な心境だと思います。
「家を出たかった」そうでは無いと思います。決して親元から逃げ
出せるという気持ちは無かったはずです。発達障害の特徴ですが、
独立心は持てないのが普通です。干渉は嫌いますが、慎重に物事を
推し進めることが苦手ですし、多くの情報を素早く処理することも
苦手です。そのせいで失敗することも多いので、一人暮らしに憧れる
ことは有っても、いざ本当に一人で暮らさなければならないという
事になれば、相当に狼狽すると思います。
ただ。今、言ったように「憧れ」は持てるんです。つまり「兄達」が
一人暮らしをするのに自分は出来ない。出来なかったという事が、
息子にとっては「負けた」「置いていかれた」と受け取っているのでは
ないかと想像しています。
また強いブラザーコンプレックスを持っていて、憧れの対象であり、
無二の親友が家からいなくなってしまうという事実が受け入れられな
いでいたと思います。上の息子達の巣立ちが決定したときに私は
覚悟を決めて言いました。中々言い出せなかったことを。
「もう響は出て行ってしまうんだ」
「お前達が、その後を継がないでどうする」
「もう甘える相手はいないんだ」
「しっかりしろ」
「いつまで、そんな態度でいるんだ」
「恥ずかしくないのか」
「響の気持ちを考えたことが有るのか」
「黙って、いつも以上に一生懸命に家の事をやっているのは」
「お前達にちゃんとして欲しいからだ」
「それを言葉でなくて態度で示しているんだ」
「分からないのか」
「あいつは、後は頼むぞって、お前達に託したいんだ」
もっと言ったかもしれません。子供たちは固まりました。いつもなら
聞き分けないです。でも「響」という名前は大きかったようです。
こんなこと言われなくても子供たちは分かっていたと思います。
この数ヶ月、長男は物凄くテキパキと積極的に、いつも以上に親の
頼みを聞いてくれて、家事を手伝ってくれました。それは「後姿」で
弟や妹達に「やれば出来ること」を恣意的な態度で誤魔化して、
大切な「家庭」の雰囲気を壊してはいけないと教えていたんだと
誰もが分かっていたはずです。
でも親を含めて子供たちは長男が家から居なくなることを受け入れ
たく無かったのかもしれません。
三男の変化は顕著でした。これからは、お前が響の代わりだと
言うと、自分でも、それを受け入れたようでした。私が居なければ
家には三男しか男は居ません。やはり勝手な振る舞いで家庭の
雰囲気を壊している場合ではないのです。分かっていたんだと
思います。しゃべるようになりました。
6年ぶりくらいに普通に返事もします。自分の考えも言う様になりました。
そうなると思っていましたが、息子の「はっきりとした」声を聞くのが
実に6年ぶりくらいだったので、震える感情を押さえることが出来ずに
一人で泣いていました。長かった。
今は、まだギクシャクしています。きっと無理をしているんです。
ですが、これがルーティンになれば寛解してゆくスピードは速まると
思います。もうひとつ我慢しています。
息子は長男が出て行くときも、次男が出て行くときも寝たままで
起きもせず「別れの言葉」を言いませんでした。とても別れを受け入れら
れないと思っていたので、私も家内も三男を、そっと寝かせて置きました。
いつの間にか居なくなってしまった兄。
息子は出て行った主人を待っている犬のような心境で日々を送っている
のではないかと思います。私の気持ちに似ています。
ですが、感傷的では無いのです。息子は、そういう性格なのです。
受け入れがたい「辛いこと」を他人事、非現実的なこと、結論が出て
いないことだと「自分の殻」に閉じこもって受け入れないようにするのです。
自閉症です。
だから口数が少ないんです。私も小さな頃は全く同じでした。
大人が苦手というより嫌いでした。息子は一生懸命に「大人」になろうと
しているということです。
「そうだ俺も兄貴達みたいに大人になろう」そう考えているように感じて
なりません。この子も大変に見ていて辛いです。
出て行った子供も辛いはずです。でも、もしかしたら残って一人になった、
この子が一番辛いのかもしれません。いつもいつも上の二人の真似をして
いた旋律。長男が小学校の1年生、次男が年中さん、三男が年少さんの
頃だったと思いますが、散歩に出た家の裏の茶畑で長男と次男が
「立ちションベン」をしているのを見て、三男が、いきなりズボンを下ろし、
小さなオチンチンをポロンと出して、シャーっとオシッコをしたのを良く覚えて
います。三人でオシッコのアーチを描いているのを見て私は大笑いしました。
可笑しかった。
なんでも真似するんだなとシミジミと思ったものです。
なあ旋律。お前、俺の一体どこが嫌いだったんだ?俺は、ずっとずっと
お前のこと大好きだぞ。GWが待ちどおしいよな。俺もお前とおんなじなんだ。


6年前の同じ日に高校の入学式を迎えました。あっという間です。
ですが振り返ると随分と色々有った6年間でもあります。
先週の土曜日に次男と三男も入学式を済ませました。
次男は東京に暮らすことになりましたが三男は自宅から通学する
ことになりました。
三男は小学校の5、6年生くらいから扱いにくくなりました。
中学に入ると顕著になった反抗的な態度。でも反抗とは違うような、
なんとも掴みどころのない不思議な世界を貫いていました。
反抗期ではないんです。
三男は我が家では一番発達障害が顕著な子供です。小さな頃から
「頑な」な正確で口数も少なかったです。余りにも、しゃべりださない
ので知的障害が有るのかもしれないと本気で心配していました。
最近になって発達障害やアスペルガー症候群のことを知ったので、
今までの様々な受け入れがたい不思議な経験を理解し、親として
受け入れられるようになりました。でも、受け入れられると言っても、
その特異な性質というか感情表現は相当に親には堪えるものでして、
一体どうすれば、まともな親子関係が築けるのかと悩みに悩み、
一人で泣いているときも随分と有りました。っていうか進行形です。
三男は公立大学の受験に失敗しました。地元の私立大学に通う
ことになりましたが、当初は浮かない表情でした。絶対に言葉には
しませんし、感情も表には出しません。それでも18年も一緒に暮らし
ていると、息子が何を考えているのか薄っすらとは分かるものです。
浮かない理由は勿論、第一志望に受からなかったことでしょう。
そして長男と次男は家を出て行くのに自分は家に残るということが
決定したからだと私は受け取っていました。
これは非常に複雑な心境だと思います。
「家を出たかった」そうでは無いと思います。決して親元から逃げ
出せるという気持ちは無かったはずです。発達障害の特徴ですが、
独立心は持てないのが普通です。干渉は嫌いますが、慎重に物事を
推し進めることが苦手ですし、多くの情報を素早く処理することも
苦手です。そのせいで失敗することも多いので、一人暮らしに憧れる
ことは有っても、いざ本当に一人で暮らさなければならないという
事になれば、相当に狼狽すると思います。
ただ。今、言ったように「憧れ」は持てるんです。つまり「兄達」が
一人暮らしをするのに自分は出来ない。出来なかったという事が、
息子にとっては「負けた」「置いていかれた」と受け取っているのでは
ないかと想像しています。
また強いブラザーコンプレックスを持っていて、憧れの対象であり、
無二の親友が家からいなくなってしまうという事実が受け入れられな
いでいたと思います。上の息子達の巣立ちが決定したときに私は
覚悟を決めて言いました。中々言い出せなかったことを。
「もう響は出て行ってしまうんだ」
「お前達が、その後を継がないでどうする」
「もう甘える相手はいないんだ」
「しっかりしろ」
「いつまで、そんな態度でいるんだ」
「恥ずかしくないのか」
「響の気持ちを考えたことが有るのか」
「黙って、いつも以上に一生懸命に家の事をやっているのは」
「お前達にちゃんとして欲しいからだ」
「それを言葉でなくて態度で示しているんだ」
「分からないのか」
「あいつは、後は頼むぞって、お前達に託したいんだ」
もっと言ったかもしれません。子供たちは固まりました。いつもなら
聞き分けないです。でも「響」という名前は大きかったようです。
こんなこと言われなくても子供たちは分かっていたと思います。
この数ヶ月、長男は物凄くテキパキと積極的に、いつも以上に親の
頼みを聞いてくれて、家事を手伝ってくれました。それは「後姿」で
弟や妹達に「やれば出来ること」を恣意的な態度で誤魔化して、
大切な「家庭」の雰囲気を壊してはいけないと教えていたんだと
誰もが分かっていたはずです。
でも親を含めて子供たちは長男が家から居なくなることを受け入れ
たく無かったのかもしれません。
三男の変化は顕著でした。これからは、お前が響の代わりだと
言うと、自分でも、それを受け入れたようでした。私が居なければ
家には三男しか男は居ません。やはり勝手な振る舞いで家庭の
雰囲気を壊している場合ではないのです。分かっていたんだと
思います。しゃべるようになりました。
6年ぶりくらいに普通に返事もします。自分の考えも言う様になりました。
そうなると思っていましたが、息子の「はっきりとした」声を聞くのが
実に6年ぶりくらいだったので、震える感情を押さえることが出来ずに
一人で泣いていました。長かった。
今は、まだギクシャクしています。きっと無理をしているんです。
ですが、これがルーティンになれば寛解してゆくスピードは速まると
思います。もうひとつ我慢しています。
息子は長男が出て行くときも、次男が出て行くときも寝たままで
起きもせず「別れの言葉」を言いませんでした。とても別れを受け入れら
れないと思っていたので、私も家内も三男を、そっと寝かせて置きました。
いつの間にか居なくなってしまった兄。
息子は出て行った主人を待っている犬のような心境で日々を送っている
のではないかと思います。私の気持ちに似ています。
ですが、感傷的では無いのです。息子は、そういう性格なのです。
受け入れがたい「辛いこと」を他人事、非現実的なこと、結論が出て
いないことだと「自分の殻」に閉じこもって受け入れないようにするのです。
自閉症です。
だから口数が少ないんです。私も小さな頃は全く同じでした。
大人が苦手というより嫌いでした。息子は一生懸命に「大人」になろうと
しているということです。
「そうだ俺も兄貴達みたいに大人になろう」そう考えているように感じて
なりません。この子も大変に見ていて辛いです。
出て行った子供も辛いはずです。でも、もしかしたら残って一人になった、
この子が一番辛いのかもしれません。いつもいつも上の二人の真似をして
いた旋律。長男が小学校の1年生、次男が年中さん、三男が年少さんの
頃だったと思いますが、散歩に出た家の裏の茶畑で長男と次男が
「立ちションベン」をしているのを見て、三男が、いきなりズボンを下ろし、
小さなオチンチンをポロンと出して、シャーっとオシッコをしたのを良く覚えて
います。三人でオシッコのアーチを描いているのを見て私は大笑いしました。
可笑しかった。
なんでも真似するんだなとシミジミと思ったものです。
なあ旋律。お前、俺の一体どこが嫌いだったんだ?俺は、ずっとずっと
お前のこと大好きだぞ。GWが待ちどおしいよな。俺もお前とおんなじなんだ。


2019年04月07日
巣立ち その2
昨日、次男も家を出て行きました。
長男のときと違って、情緒的な別れは皆無に等しかったです。
ただ。
それは、「客観的」というか、外から見ればというか、
掻い摘んで流れを言えば、そうなるってだけです。
親としては、子供が大きな荷物を抱えて去っていく後姿を
見送るのは、やはり例え様の無い空しさを感じるものでした。
次男は去年の春、高校を卒業して地元企業に就職しました。
地元では有名な会社の関連会社です。関連会社ですが、
まぁ同じ会社です。待遇なども同じです。ちょっと考えられない
待遇でした。静岡で働いている人ならば、大抵の人は羨む
高待遇だと思います。家内も息子と同じ会社で働いていました。
ただ、高待遇では有りましたが、仕事内容は決して息子が
思い描いていたようなものでは有りませんでした。大企業という
ものは、そういった「仕方の無い」仕事を受け持つ人材も
多く必要です。大勢の人たちが互いを支えあって企業として
成り立っているのです。どうして息子が採用されたのかは
分かりませんが、今となっては「どうして」その会社に入ったのかも
分からなくなってしまいました。やはり子供には「目的」を持って
働くという「ビジョン」が見えにくい、持ちにくいということでしょう。
息子は、この春から服飾系の専門学校に通うことになりました。
息子が洋服に興味を持つようになったのは高校一年生くらい
からです。多くの子供たちが「オシャレ」に気を使う、感心を
持つようになる年頃です。まぁ普通のことです。
私もオシャレには強い関心がありました。小学校の5年生くらい
だったでしょうか、ファッションデザインに強い興味を持って、
デザイン画などを一生懸命に描いていました。将来は、ファッション
デザイナーになりたいと作文に書いた事も有ります。
そんな話をする前から、息子は、デザイナーになりたいと言い出した
のですから、これは正に蛙の子は蛙というやつです。
息子が学校に内緒でバイトを始めたのも「服を買いたいから」って
理由です。彼女も出来ましたが、友達と遊びに行っても食事代など
にお金を使うことは限りなくゼロに近かったと思います。
友達のクーポンまで利用してマックでポテトだけを「ただ」で食べて
良しとして来たなんて数えたらキリが有りません。ちびちび小遣いを
せびっていきましたが、息子がファッションに興味を持ったことが
私には痛快で、ついつい服を買ってあげてしまったり、私の「お古」を
出してきて、サイズが合えば着れば良いと渡していました。
息子は「しつこい」程にファッションの質問を浴びせかけてきました。
発達障害の特徴ですかね。一度、興味が湧くと止まらなくなります。
何度も同じことを聞いてきます。偏執的になって、デザイナーの
名前だけでなく、その生い立ちや出自まで。ブランドの起源や、
それらのマーケティング、社長の年収にまで興味を持ちます。
実は私も服飾に関しては結構な知識があったので、息子のQに対して
直ぐにAを出せるという関係が、益々息子の服飾への関心を煽って
いったのかもしれません。
では、なぜ息子は高校卒業と同時に専門学校に行かなかったのでしょう。
それには、いくつか理由があります。これも私の過去と類似しています。
息子には交際していた彼女がいました。高校生くらいの恋です。
一時も離れていたくは無かったんだと思います。我が家の経済状況も
進路を考える上で大きな要因になったと思います。高校生くらいの頃は
口も重くなります。親を気遣ってということもあったでしょう。
年がら年中、金の無い騒ぎをしている我が家です。とても専門学校に
通わせてくれとは言えなかったのかもしれません。奨学金という手も
有ったのですが、それは「借金」だと息子は考えていたようです。
勿論そうです。
奨学金は将来の自分への投資です。最初から無駄になると思ったら、
それは無駄遣い。下らない時間つぶしのための金。借金になるだけです。
しかし本気で「学び」に向かっていくのなら、使って当然の金だと思います。
つまり、ここです。息子は「がち」に成り切れなかったということだと思います。
それは彼女の存在だったり、「発達障害」である自分に自信が持てない
という「不安」が、親元を離れて「一人暮らし」が出来ないという結果に
結びついたのではないかと思っています。
高校を卒業後、当初は「独立」を宣言していました。これは「一人暮らし」では
ありません。つまり「同棲」を始めるという宣言です。会社に通うには、
山を下りた方が便利ですし、市街地に暮らしていた方が相当に豊かに
暮らせると考えたからでしょう。全く、その通りです。彼女と「なあなあ」の
暮らしについて反対しないはずが有りません。息子は彼女の御両親にも
大変に可愛がって頂いて、ご自宅に下宿させても良いとさえ言って頂きました。
私たち夫婦は益々それでは問題だと考えました。当然です。18歳になった
ばかりの「子供」が結婚するのかも、どうかも分からないで、可能性という
ものを「固定して」生きて行くなどと、まともな親なら許すはずがありません。
破局したらどうするつもりだろうと。
案の定、高校卒業後、ものの1ヶ月くらいで息子は振られてしまいました。
抜け殻のような生活になりました。毎日の送り迎えの車中で、息子に
沢山話しかけますが、その答えは、どこかうつろで、私まで泣いてしまい
そうになりました。気持ちが落ち着くまで結構な時間を要しました。
ご他聞に漏れず、失恋は新しい恋でしか癒されないという感じで、数ヶ月する
と新しい彼女が出来、家族にも紹介してくれましたが、なんか息子には
合わない子だなと思ったとおり、極々短期間で息子は振られました。
誰の目から見ても美男子だと映る息子ですが、やはり中身で付き合うものです。
息子の「足りない」ところが同い年の女の子には幼すぎると感じるのでしょうか、
どうしても長続きしません。
この年頃の男子は同じような経験をするはずです。私も全く同じでした。
このようにプライベートでも気が重くなるようなことが続き、更に悪いことに
職場で嫌がらせを受けるようになりました。息子の勤務態度が悪かったと
思いますが、悪いときに、きつい言葉を浴びせかけられたのだと思います。
職場の皆さんは息子よりも大人で、本当に良くして頂いたと本人も言っていました。
もっともっと頑張って、会社に馴染もうと、もがけばもがくほど、意地の悪い
先輩の一言が重くのしかかってきたようです。私は会社を辞めれば良いと
言いました。そんな頃に、あのデザイナーへの憧れが再び頭をもたげ、
別の道で夢を見たいと強く考えるようになったのです。会社を辞める決心をして
からは、少しだけ勤めに行くのも元気が出たように見えました。
会社のみなさんに退職して服飾の専門学校に行きますと打ち明けてから、
全く揉めることなく、一時の感情ならばと引き止めて頂いたのですが、
最終的には考えを後押しして頂いて、「本多君の作った服を着てみたいから、
頑張ってね。」「そのときが来るのを楽しみにしているから」「きっと連絡して
きてくれよな」と言って頂いた先輩もいらっしゃったそうです。
聞いていて涙が溢れました。そう静かに教えてくれた息子の目にも薄っすらと
涙がありました。ありがたかったです。
学校を選びました。息子に尋ねられました。専門学校なら、どこが良いと。
良い、悪いは分かりませんでしたが、建築と同じように日本でデザインを
学びたいのなら、それはもう当然、東京しか考えられません。何校か有名な
学校が有りますが、私でさえ知っている「専門学校」を教えて上げました。
すると息子の友人も何人か、そこに通っていると答えました。良い部分も
悪い部分も、ある程度理解して、その学校にへ進学することになりました。
ただ、息子の悪い癖で何事もギリギリなのです。
結局、奨学金の予約採用も申し込みませんでしたし、受験の申し込みも最終日に
「私が」出してきましたし。合格は出来たのですが、とうとう「アパート」も見つからず、
というか借りる「貯金」も底をついて、結局、友達の家に居候するという。
暫くバイトして、落ち着いたらアパートを借りて一人暮らしをするらしいです。
勝手にしてくれ。
入学式も6日なのに出て行ったのは6日の朝。ドタバタです。朝の5時過ぎに
起きて、大慌てで家を出ました。しかし山道の途中で書類を忘れたとUターン。
もう新幹線には間に合わないだろうとなって、執拗に夫婦揃って
「お前というやつは」と散々息子を叱り飛ばし、息子もすっかり意気消沈して。
それでも土曜日の朝ということもあって、奇跡的に新幹線の時間に間に合いそうな
時間に駅に到着できました。しかし、またもノロノロと荷物を持ったり、支度を
している息子に「さっさとしろっ!!」と、どやさなければならず。こちらも情けなくて、
物凄い脱力感に支配されたのでした。息子は「行きたくなかった」んです。
分かっていました。発達障害です。自立して全てを完璧になんて出来やしないです。
物凄くバイタリティーがあるように見えますが違います。なんでもこなしますが、
「一人」が駄目なんです。私と一緒です。私は家内がいないと何も出来なくなります。
全く役に立たないのですが、いてくれないと不安になってしまうのです。それまでも
そうでした。彼女だったり友人だったり、母だったり。誰かが確実に寄り添っていて
くれるという安心感がないと全く勇気が出てきません。
実は巣立って行くことになって、今頃になって、また新しい彼女が出来たんです。
ああ...
家を出て行く2日前に彼女を家に連れてきました。長身の美人でした、明るく
優しい感じが一瞬で伝わってきます。こりゃ駄目だと私も家内は思いました。
この「静岡の彼女」がいる限り東京での一人暮らしの成功の可能性は限りなく低く、
そもそも明日、愚息は家を出て行けるのかなとさえ思いました。案の定です。
物凄く足取りは重く見えました。馬鹿野郎...
「行ってきます」小さく、か細い声。
息子は、そう言って大きなキャリーケースを引きずって歩き始めました。
後姿に向かって家内が「おい拍!!何か有ったら電話してくるんだよ!!」
「無理しないで、何でも言いなよ!!」と叫びました。さっきまで鬼のような形相だった
「母親」は眉を八の字にして不安で一杯という表情で息子に向かってエールを
送りました。大粒の涙は流しませんでしたが、夫婦ともども心の中は、土砂降りの雨の
ように涙を流していました。息子は振り返りもせず駅ビルに消えていきました。
振り返られなかったんだと思います。私たちは車に乗り込みました。
家内が「忘れ物は無いな?!」と後ろの席に座っていた長女と三女に声をかけました。
娘達は「どうでもいい」という、けだるい表情で「無いよ」と言いました。
でも私は、嫌そんなことは無い、あいつは忘れる。忘れて当たり前のやつだと思い、
助手席の後ろの収納に手を入れました。有りました。入学手続きの書類の封筒が。
これを取りにわざわざ山道を引き返したのに。
私は封筒を掴むと駅ビルに向かって走りました。息子は階段をゴトゴトとキャリーケース
を引きずって、やっと下りたところでした。私のバタバタと掛けて来る足音に気が付いて
息子は振り返りました。私は怒った顔をしていたと思います。息子に向かって
封筒を突き出しました。息子は一瞬「あっ」という表情をしました。息子の心境は
手に取るように分かりました。「ごめんなさい」息子の口癖です。「ごめんなさい」、
息子は、そう言いたかったんだと思います。「ありがとう」ではありません。
「ごめんなさい」なんです。いつもいつも叱られてばかりです。発達障害の宿命です。
結局は叱られてしまうんです。時間もギリギリ。なにをするにもギリギリ。
私は「おいっ!!しっかりしろよ!!」と大きな声で息子に言いました。
息子は返事をしませんでした。生まれて初めてです。寂しそうな目で私を見つめて、
また振り返ると駅ビルの中に去って行きました。私はガラスの向こうに息子の姿が
霞んでいくのをじっと見ていました。すると息子が振り返りました。ほんの一瞬だけ
息子は振り返りました。目が合いました。きっと息子は振り返ると思いました。
息子は私が、いつまでも自分の後姿を見ていてくれると信じていたと思います。
だからそれを「確認」したかったんだと思います。「やっぱり見ていてくれた」
きっと息子は、そう思ったと思います。
離れていても、いつまでも見つめていたいです。息子の傍には今は誰もいません。
でも息子は自分が孤独でないと感じていると思います。それが親子の絆だと私は
思っています。別れたばかりなのに、早く息子に会いたいです。長男にも会いたいです。
今朝送っていったばかりの娘達にも早く帰ってこないかなと、毎日考えながら
一日過ごしています。私は酷く不完全な人間です。家族がいなければ自分が、
どういうものなのかすら説明できません。
ここ数日、仕事が手につきません。子供たちに何か楽しい出来事は有ったでしょうか。
どこにいても笑顔を忘れないで生きていって欲しいと思います。
息子を送って山に帰りました。暫くして三男を入学式の会場に送るために再び
下山しました。息子達が通った中学校の近くの土手の桜が満開に咲いていたので
記念写真を撮りに寄りました。すると家内の携帯に次男から写真が送られてきました。
「おわったよ」
そうメッセージが添えられた写真には、はにかんだ笑顔と満開の桜が写っていました。
愛してるよ拍。頑張れよ!!

長男のときと違って、情緒的な別れは皆無に等しかったです。
ただ。
それは、「客観的」というか、外から見ればというか、
掻い摘んで流れを言えば、そうなるってだけです。
親としては、子供が大きな荷物を抱えて去っていく後姿を
見送るのは、やはり例え様の無い空しさを感じるものでした。
次男は去年の春、高校を卒業して地元企業に就職しました。
地元では有名な会社の関連会社です。関連会社ですが、
まぁ同じ会社です。待遇なども同じです。ちょっと考えられない
待遇でした。静岡で働いている人ならば、大抵の人は羨む
高待遇だと思います。家内も息子と同じ会社で働いていました。
ただ、高待遇では有りましたが、仕事内容は決して息子が
思い描いていたようなものでは有りませんでした。大企業という
ものは、そういった「仕方の無い」仕事を受け持つ人材も
多く必要です。大勢の人たちが互いを支えあって企業として
成り立っているのです。どうして息子が採用されたのかは
分かりませんが、今となっては「どうして」その会社に入ったのかも
分からなくなってしまいました。やはり子供には「目的」を持って
働くという「ビジョン」が見えにくい、持ちにくいということでしょう。
息子は、この春から服飾系の専門学校に通うことになりました。
息子が洋服に興味を持つようになったのは高校一年生くらい
からです。多くの子供たちが「オシャレ」に気を使う、感心を
持つようになる年頃です。まぁ普通のことです。
私もオシャレには強い関心がありました。小学校の5年生くらい
だったでしょうか、ファッションデザインに強い興味を持って、
デザイン画などを一生懸命に描いていました。将来は、ファッション
デザイナーになりたいと作文に書いた事も有ります。
そんな話をする前から、息子は、デザイナーになりたいと言い出した
のですから、これは正に蛙の子は蛙というやつです。
息子が学校に内緒でバイトを始めたのも「服を買いたいから」って
理由です。彼女も出来ましたが、友達と遊びに行っても食事代など
にお金を使うことは限りなくゼロに近かったと思います。
友達のクーポンまで利用してマックでポテトだけを「ただ」で食べて
良しとして来たなんて数えたらキリが有りません。ちびちび小遣いを
せびっていきましたが、息子がファッションに興味を持ったことが
私には痛快で、ついつい服を買ってあげてしまったり、私の「お古」を
出してきて、サイズが合えば着れば良いと渡していました。
息子は「しつこい」程にファッションの質問を浴びせかけてきました。
発達障害の特徴ですかね。一度、興味が湧くと止まらなくなります。
何度も同じことを聞いてきます。偏執的になって、デザイナーの
名前だけでなく、その生い立ちや出自まで。ブランドの起源や、
それらのマーケティング、社長の年収にまで興味を持ちます。
実は私も服飾に関しては結構な知識があったので、息子のQに対して
直ぐにAを出せるという関係が、益々息子の服飾への関心を煽って
いったのかもしれません。
では、なぜ息子は高校卒業と同時に専門学校に行かなかったのでしょう。
それには、いくつか理由があります。これも私の過去と類似しています。
息子には交際していた彼女がいました。高校生くらいの恋です。
一時も離れていたくは無かったんだと思います。我が家の経済状況も
進路を考える上で大きな要因になったと思います。高校生くらいの頃は
口も重くなります。親を気遣ってということもあったでしょう。
年がら年中、金の無い騒ぎをしている我が家です。とても専門学校に
通わせてくれとは言えなかったのかもしれません。奨学金という手も
有ったのですが、それは「借金」だと息子は考えていたようです。
勿論そうです。
奨学金は将来の自分への投資です。最初から無駄になると思ったら、
それは無駄遣い。下らない時間つぶしのための金。借金になるだけです。
しかし本気で「学び」に向かっていくのなら、使って当然の金だと思います。
つまり、ここです。息子は「がち」に成り切れなかったということだと思います。
それは彼女の存在だったり、「発達障害」である自分に自信が持てない
という「不安」が、親元を離れて「一人暮らし」が出来ないという結果に
結びついたのではないかと思っています。
高校を卒業後、当初は「独立」を宣言していました。これは「一人暮らし」では
ありません。つまり「同棲」を始めるという宣言です。会社に通うには、
山を下りた方が便利ですし、市街地に暮らしていた方が相当に豊かに
暮らせると考えたからでしょう。全く、その通りです。彼女と「なあなあ」の
暮らしについて反対しないはずが有りません。息子は彼女の御両親にも
大変に可愛がって頂いて、ご自宅に下宿させても良いとさえ言って頂きました。
私たち夫婦は益々それでは問題だと考えました。当然です。18歳になった
ばかりの「子供」が結婚するのかも、どうかも分からないで、可能性という
ものを「固定して」生きて行くなどと、まともな親なら許すはずがありません。
破局したらどうするつもりだろうと。
案の定、高校卒業後、ものの1ヶ月くらいで息子は振られてしまいました。
抜け殻のような生活になりました。毎日の送り迎えの車中で、息子に
沢山話しかけますが、その答えは、どこかうつろで、私まで泣いてしまい
そうになりました。気持ちが落ち着くまで結構な時間を要しました。
ご他聞に漏れず、失恋は新しい恋でしか癒されないという感じで、数ヶ月する
と新しい彼女が出来、家族にも紹介してくれましたが、なんか息子には
合わない子だなと思ったとおり、極々短期間で息子は振られました。
誰の目から見ても美男子だと映る息子ですが、やはり中身で付き合うものです。
息子の「足りない」ところが同い年の女の子には幼すぎると感じるのでしょうか、
どうしても長続きしません。
この年頃の男子は同じような経験をするはずです。私も全く同じでした。
このようにプライベートでも気が重くなるようなことが続き、更に悪いことに
職場で嫌がらせを受けるようになりました。息子の勤務態度が悪かったと
思いますが、悪いときに、きつい言葉を浴びせかけられたのだと思います。
職場の皆さんは息子よりも大人で、本当に良くして頂いたと本人も言っていました。
もっともっと頑張って、会社に馴染もうと、もがけばもがくほど、意地の悪い
先輩の一言が重くのしかかってきたようです。私は会社を辞めれば良いと
言いました。そんな頃に、あのデザイナーへの憧れが再び頭をもたげ、
別の道で夢を見たいと強く考えるようになったのです。会社を辞める決心をして
からは、少しだけ勤めに行くのも元気が出たように見えました。
会社のみなさんに退職して服飾の専門学校に行きますと打ち明けてから、
全く揉めることなく、一時の感情ならばと引き止めて頂いたのですが、
最終的には考えを後押しして頂いて、「本多君の作った服を着てみたいから、
頑張ってね。」「そのときが来るのを楽しみにしているから」「きっと連絡して
きてくれよな」と言って頂いた先輩もいらっしゃったそうです。
聞いていて涙が溢れました。そう静かに教えてくれた息子の目にも薄っすらと
涙がありました。ありがたかったです。
学校を選びました。息子に尋ねられました。専門学校なら、どこが良いと。
良い、悪いは分かりませんでしたが、建築と同じように日本でデザインを
学びたいのなら、それはもう当然、東京しか考えられません。何校か有名な
学校が有りますが、私でさえ知っている「専門学校」を教えて上げました。
すると息子の友人も何人か、そこに通っていると答えました。良い部分も
悪い部分も、ある程度理解して、その学校にへ進学することになりました。
ただ、息子の悪い癖で何事もギリギリなのです。
結局、奨学金の予約採用も申し込みませんでしたし、受験の申し込みも最終日に
「私が」出してきましたし。合格は出来たのですが、とうとう「アパート」も見つからず、
というか借りる「貯金」も底をついて、結局、友達の家に居候するという。
暫くバイトして、落ち着いたらアパートを借りて一人暮らしをするらしいです。
勝手にしてくれ。
入学式も6日なのに出て行ったのは6日の朝。ドタバタです。朝の5時過ぎに
起きて、大慌てで家を出ました。しかし山道の途中で書類を忘れたとUターン。
もう新幹線には間に合わないだろうとなって、執拗に夫婦揃って
「お前というやつは」と散々息子を叱り飛ばし、息子もすっかり意気消沈して。
それでも土曜日の朝ということもあって、奇跡的に新幹線の時間に間に合いそうな
時間に駅に到着できました。しかし、またもノロノロと荷物を持ったり、支度を
している息子に「さっさとしろっ!!」と、どやさなければならず。こちらも情けなくて、
物凄い脱力感に支配されたのでした。息子は「行きたくなかった」んです。
分かっていました。発達障害です。自立して全てを完璧になんて出来やしないです。
物凄くバイタリティーがあるように見えますが違います。なんでもこなしますが、
「一人」が駄目なんです。私と一緒です。私は家内がいないと何も出来なくなります。
全く役に立たないのですが、いてくれないと不安になってしまうのです。それまでも
そうでした。彼女だったり友人だったり、母だったり。誰かが確実に寄り添っていて
くれるという安心感がないと全く勇気が出てきません。
実は巣立って行くことになって、今頃になって、また新しい彼女が出来たんです。
ああ...
家を出て行く2日前に彼女を家に連れてきました。長身の美人でした、明るく
優しい感じが一瞬で伝わってきます。こりゃ駄目だと私も家内は思いました。
この「静岡の彼女」がいる限り東京での一人暮らしの成功の可能性は限りなく低く、
そもそも明日、愚息は家を出て行けるのかなとさえ思いました。案の定です。
物凄く足取りは重く見えました。馬鹿野郎...
「行ってきます」小さく、か細い声。
息子は、そう言って大きなキャリーケースを引きずって歩き始めました。
後姿に向かって家内が「おい拍!!何か有ったら電話してくるんだよ!!」
「無理しないで、何でも言いなよ!!」と叫びました。さっきまで鬼のような形相だった
「母親」は眉を八の字にして不安で一杯という表情で息子に向かってエールを
送りました。大粒の涙は流しませんでしたが、夫婦ともども心の中は、土砂降りの雨の
ように涙を流していました。息子は振り返りもせず駅ビルに消えていきました。
振り返られなかったんだと思います。私たちは車に乗り込みました。
家内が「忘れ物は無いな?!」と後ろの席に座っていた長女と三女に声をかけました。
娘達は「どうでもいい」という、けだるい表情で「無いよ」と言いました。
でも私は、嫌そんなことは無い、あいつは忘れる。忘れて当たり前のやつだと思い、
助手席の後ろの収納に手を入れました。有りました。入学手続きの書類の封筒が。
これを取りにわざわざ山道を引き返したのに。
私は封筒を掴むと駅ビルに向かって走りました。息子は階段をゴトゴトとキャリーケース
を引きずって、やっと下りたところでした。私のバタバタと掛けて来る足音に気が付いて
息子は振り返りました。私は怒った顔をしていたと思います。息子に向かって
封筒を突き出しました。息子は一瞬「あっ」という表情をしました。息子の心境は
手に取るように分かりました。「ごめんなさい」息子の口癖です。「ごめんなさい」、
息子は、そう言いたかったんだと思います。「ありがとう」ではありません。
「ごめんなさい」なんです。いつもいつも叱られてばかりです。発達障害の宿命です。
結局は叱られてしまうんです。時間もギリギリ。なにをするにもギリギリ。
私は「おいっ!!しっかりしろよ!!」と大きな声で息子に言いました。
息子は返事をしませんでした。生まれて初めてです。寂しそうな目で私を見つめて、
また振り返ると駅ビルの中に去って行きました。私はガラスの向こうに息子の姿が
霞んでいくのをじっと見ていました。すると息子が振り返りました。ほんの一瞬だけ
息子は振り返りました。目が合いました。きっと息子は振り返ると思いました。
息子は私が、いつまでも自分の後姿を見ていてくれると信じていたと思います。
だからそれを「確認」したかったんだと思います。「やっぱり見ていてくれた」
きっと息子は、そう思ったと思います。
離れていても、いつまでも見つめていたいです。息子の傍には今は誰もいません。
でも息子は自分が孤独でないと感じていると思います。それが親子の絆だと私は
思っています。別れたばかりなのに、早く息子に会いたいです。長男にも会いたいです。
今朝送っていったばかりの娘達にも早く帰ってこないかなと、毎日考えながら
一日過ごしています。私は酷く不完全な人間です。家族がいなければ自分が、
どういうものなのかすら説明できません。
ここ数日、仕事が手につきません。子供たちに何か楽しい出来事は有ったでしょうか。
どこにいても笑顔を忘れないで生きていって欲しいと思います。
息子を送って山に帰りました。暫くして三男を入学式の会場に送るために再び
下山しました。息子達が通った中学校の近くの土手の桜が満開に咲いていたので
記念写真を撮りに寄りました。すると家内の携帯に次男から写真が送られてきました。
「おわったよ」
そうメッセージが添えられた写真には、はにかんだ笑顔と満開の桜が写っていました。
愛してるよ拍。頑張れよ!!

2019年04月05日
大学選び
昨日の受験記の続きです。
早稲田大学の補欠の発表が終わって、信州大学と日大と、
どちらの学校に入学するのが良いのだろうと「親目線」で
真剣に考えるようになりました。決して、この時点では
「建築家」としてでは有りませんでした。
息子の気持ちを最優先に考えていました。学校に通うのは
当の本人ですから。当たり前のことです。
ネットの情報を死ぬほど漁りました。中々結論が導き
出せなかったからです。それは昨日の記事にも書いたように
「思い込み」は大きく間違った選択をする危険が有るという
ことを嫌という程知ったからです。
息子の高校受験のときに偏差値の高い順に「良い学校」だと
妄信的になっていて、この学校に入れば「良い大学」に入れる
だろうと、馬鹿なことを考えていました。あながち全く間違った
考えではないのですが、受験というよりも「勉強」なんてものは、
「本人次第」な訳です。少々厳しく課題を出されたりした程度では、
とても学力なんて定着しません。逆に宿題を山ほど出しておいて、
ろくに提出物に対して評価や指導をしない学校では自分の
時間が取れなくて学力は低下するはずです。それに進学校
なのにムキニなって部活をやらせるのも子供たちには負担に
なるはずです。得られるものも多いでしょうけれど「失うもの」が
れっきとして存在することを肝に銘じておいて欲しいです。
息子の通った学校は正に、そのような学校でした。
入学したばかりのときは、いわゆるトップ校との差は僅差という
より「ほぼ無い」という状態の成績の子供たちばかりなのに、
卒業する頃には、その差は簡単には埋められないほどの
実力差になってしまっています。息子は遠距離の通学という
ことも有って、部活は文化部。いわゆる帰宅部でしたが、通学に
時間をとられて、宿題も深夜まで掛かってやっていました。
このガッツは、トップ校の生徒に負けたくないという「意地」でも
あったと今は思っています。御蔭で成績は好ましい状態でしたが、
所詮は校内の成績です。2年生くらいまでの模試でも志望校の
合格判定はA、Bを出していましたが、早すぎる模試の結果は、
丸で当てになりません。
現役のときに受けたセンター試験の結果を「合格判定システム」に
掛けて、担任の先生は「矢継ぎ早に」「ここはどう?こっちはどう?」
などと、丸でユニクロにフリースでも買いに行ったように「適当に」
偏差値だけで合格しそうな大学が記載された紙をベラベラと
息子と私の前で何枚も出し続けたのでした。これが「進路指導」です。
呆れました。全く信頼できませんでした。
入学したときのガイダンスでは男性教諭が「私の息子は静高に
通っていますが、進路相談なんて全くしてくれませんよ」「東校は
本当に親身になってやっていますから、良い学校に入学されました」と
堂々と言ってのけていました。
その静岡高校も浪人生ばかりを大量に排出しています。大変に
自由で私は好きですね(笑)実は大抵の家庭の親御さんも、
お子さんの進学先を「適当」に決めているのではないかと思います。
私のように大学受験の経験も無ければ尚更だと思います。
私の場合「自由」を最も大切にしていますから、基本的には
「子供の自主性」に任せています。悪い言い方をすれば「勝手に」
すれば良いということでしょうか。ただ、私は、そういった「そぶり」は
見せていますが、ちゃんとバックアップを取っておくということに、
相当に気を使っています。そうです子供の選択が妥当かどうかです。
正しい、間違っているではありません。
現役のときに受けた千葉大学は良い仕事をしている建築家が結構
出ていると認識がありました。私は最近相当に評判の良い
横浜国立大学の建築コースを出られて、仕事に恵まれた建築家を
余り知らなかったので、わざわざ大変な思いをして「偏差値」に拘って
受験することもないと子供には言いました。話に聞くと新しい情報では
横国の教授には相当な方がいらっしゃるとか。また設備も日本一くらいの
レベルだそうで、人気が高いのも頷けるという状態らしいです。
建築というか、建築設計の世界の中にいると、やはり東大を出た
建築家の仕事は「羨望」の的だと感じます。強がりを言ってみても、
やはり「こんな仕事をしてみたい」と思わない能力の高い建築家は、
いないでしょう。東大を出ているということは設計の能力とは全く関係の
無いところで「別の」チャンスをもたらせてくれるのは事実です。
では東大が無理だったら次は「どの大学」でしょう。
多くの受験生は「そこが」気になるのです。毎年大勢の建築家志望の
子供たちが大学を受験します。様々な境遇に有ります。
話を戻します。
大学に行く意味を改めて私は考えてみました。私は独立当初から
海外の設計コンペに挑戦して来ました。海外の設計コンペは「All」と
書かれているものが多いです。つまり誰でも参加できるということです。
出身大学というか、資格さえ問われないことが多いのです。
それは建築を芸術だと捉えている部分が大きく影響していると思います。
勿論、大規模建築物には建築の専門的な知識や要素が有って、初めて
成り立ちます。いや小規模な家や小屋でさえそうです。
ですから誰でも提案できるといっても、当然それらが、
ちゃんと成立していなければコンペで勝つことは出来ません。
従ってデザインやコンセプトなど「独自性」のあるものは自ら創造できても、
それに付随する知識や能力、また「判断力」「判断材料」を学ぶために
大学に進学することが息子には必要であり、有意義な時間と金の
使い方だと結論付けたのです。
今更ですが「大学」ではなくて「誰が」私の息子に建築を教えてくれるのか?
が最も大切だと気が付いたのです。調べました。
信大の工学部建築学科は「たったの59人」しか合格できません。
前期で44人後期で15人。後期の倍率は9.9倍です。大変に狭き門です。
10人に一人しか合格できません。どうしてこんなにも大勢の受験生が
殺到するのでしょうか。考えました。
国立大学といえば誰もが知っているように「学費」が安いことが上げられます。
大学を選ぶときに当然「受かりそう」な大学を選ぶ訳ですが、
偏差値が中間に近づくにつれて構成する人口も増える訳ですから、
当然激戦になる訳です。出来るだけ安い学費で済ませたいと考えるのは
人情でしょう。成績の優秀な子供たちが多く合格して行くのは必然です。
このことから国立大学は優秀な生徒が集まる。国立大学は良い大学だと
認知されているのだと思います。間違ってはいません。さて私が信大の
工学部建築学科を調べた結果ですが、意匠の研究室は、一つだけしか
ありません。デザインや設計の専門科目の授業も少し少ないなと感じました。
印象としては「工学部」だなぁという感じです。当たり前の話ですが、
工学部では工学的な勉強をします。東大や京大など旧帝大や国立大学の
多くは「工学部」の中の建築学科です。つまり建築の研究をするというよりは、
社会で役に立つ技術の習得が「まずは」第一目標になっている訳です。
そうは言っても、やはり建築家の養成をするクラスも有るわけです。
東大などは、やっとこ3年生になってから本格的に建築を勉強する訳ですが、
下手をすると成績によっては全く違う学科に追いやられてしまうのです。
これは他の大学でもそうです。仮にデザイン寄りの勉強をしたくても、
設計の成績が悪ければ構造や計画などの教室に振り分けられてしまいます。
それでも意匠設計のクラスが多くあればチャンスは広がります。もっとも
生徒数が多ければ比例してクラスが多くなるというだけで、果たして
60人の生徒と300人の生徒では5倍のクラスが、なければ平等とは
言えませんが、やはり教授の質には関心が残ります。
信大で刺激的な4年間が送れるのか。物凄く気になりました。
それは勿論、本人次第なのですが、クラスメートや教授に影響される部分は、
相当に有ると思うのです。
私立大学と授業料を比べると軽く年間で100万円を超えるほど差もあります。
どんなに早稲田の建築が良くても東工大に受かったら、そちらに進学する
のだろうと思います。普通の考え方です。それでも早稲田の建築は
日本一人気の有る大学です。多くは「就職に有利」だからだと言われます。
ですが、この就職については、余程の大学でもなければ大差の無い就職先で、
日大理工の就職率は97%以上です。理科大も芝工も立派なものです。
それでも東大、京大、早稲田の人気が高いのは、やはり「偏差値」で
学校を選んでいるからだと思うのです。正直、東大と早稲田の建築学科は、
魅力的なカリキュラムです。プロの私から見ても、最先端を意識して
学生達を切磋琢磨させていると、はっきりと目に映ります。
もしかすると偏差値の低い学校では、ろくに勉強もしない、態度の悪い
生徒もいて、ゼミの雰囲気を悪くしているのでは、ないだろうかと心配に
なっている受験生や親御さんが多くいるのではないかと想像します。
私も心配しました。だからきっと偏差値の高い難関大学は信頼されている
のだと思うのです。でも今語っている「偏差値」について、一概に唯一の
判断材料として良いかどうか、先程らい語っているように危険ですらあると
私は気が付いたのです。それを息子に話しました。
ええ、信大の合格発表前なのにです。馬鹿げた話なのですが、正直、信大は
絶対に受かっていると思っていました。受ける前からです。早稲田が補欠に
なった時点で、京大の結果も、そんなに悪くなかっただろうと想像しました。
偏差値で行けば早稲田も京大の建築も同じくらいです。補欠者は40人程度
でしたから合格者との点差は10点も20点もあった訳ではありません。
もしかすると1点差が有るかどうかってことだって有り得ます。そこから
判断するに信大の後期の偏差値は越えていたと考えたからです。
長野市に向かう車中で家内に私の考えを話しました。これは根拠に乏しい
ような持論を含めてです。反論を承知で書きます。あくまで持論です。
日本で建築を勉強するなら、やはり東京が一番良いと思います。
なぜなら名建築が山のように在るからです。本の中で見た気になる建築を
自分の目で簡単に見に行くことが出来ます。オープンデスクでも、
入れてもらえるか、どうかは、さておいても、聞いた事の有る名前の
建築家の設計事務所を訪ねて行くことが出来るのです。学校や研究室を
超えて、繋がって刺激し合い、洗練されて行くことが出来ると感じるからです。
私は信大に合格できても日大に行った方が良いと思いました。
家内も同意しました。
試験を終えたばかりの息子に今まで相当に研究し、また考察した私の結果を
「勇気」を出して伝えました。勇気が必要になったのは、それが「日大」だからです。
私たちの年代ですと日大は「日東駒専」と、ひとくくりにされて、あたかも
誰でも入れるような馬鹿大学だと揶揄されていたことを知っているからです。
そして現在でも、その馬鹿馬鹿しい偏差値偏重のせいで多くの受験生が、
間違った学校選びをしていると感じます。日大と一口に言っても医学部に
始まって、学部によって難易度の差は大変に大きいです。
その中でも理工建築学科は決して簡単に合格できるような学部ではありません。
我々建築に携わる人間にとってみれば日本の建築学部と言ったら、
東大、早稲田、日大理工です。
近いところで単科大学なら芝浦工業大学の建築学科も大変に優秀な学生が
多く、卒業生も素晴らしい活躍をされている方が物凄く多いです。
息子は大変に「大人しい」性格です。本当は信州大学のキャンパスの雰囲気の方が
合っていると思います。信大にいそうです(笑)でも冗談抜きにプリツカーを狙える
だけの建築家になりたいのなら、やはり刺激を受けて海外のアトリエに
勤めて欲しいと思います。もう甘えて生きる期間は終わったんだと思います。
親としては心配が増えるだけなのですが、泣いてばかりは、いられません。
息子には「これが俺の考えだ。でも行くのは、お前だ。自分で考えて結論を出せ」
そう言いました。そして私の考えを目に見える形で記憶してもらおうと、帰路を
逸れて軽井沢に向かいました。
私が建築家を志そうと決意した建築を見せたかったからです。
軽井沢高原教会です。
私たち夫婦が結婚式を挙げた教会です。ここには「ふたつの礼拝堂」があります。
私たちが挙式を上げたのは通称「木の教会」でしたが、隣接するもう一つの
礼拝堂、通称「石の教会」を、どうしても息子に見せたかったのです。
軽井沢は遠かったのですが、この機会を逃しては二度と「三人」で来ることは
叶わないだろうと思って強行しました。私たちが結婚式を挙げたときには家内の
お腹には息子が宿っていました。ですから三人で再び訪れたのは22年ぶりという
ことになります。実に感動的でした。
息子は常々私が語っているので石の教会については知っていました。
でも写真を見ただけでは、この建築物が存在する本当の意味は、ひとつも伝わらない
だろうと私は考えていたからです。石の教会は、ケンドリック・ケロッグという
アメリカ人の建築家の設計によるものです。とても特徴の有る設計をする人で、
もっともっと有名になっても良いと思うのですが、近くで教会を実施した
レーモンド程知名度はありません。私は初めて、この教会を見たときに建築物を
見ているというよりも「空間」や「成り立ち」「思想」を目で眺めることが出来るもの
なんだと深く深く感動したのを昨日の事のように覚えています。わざわざ言われなければ、
これが教会なんだとは誰の目にも映らないでしょう。内部の写真撮影は禁止されて
いるので、内部を紹介された資料は、とても少ないです。
建物の「奇異」さだけが印象に残ってしまうので、星野リゾートには、もっと内部の
画像の公開を望みたいです。内部は外観よりも更に異空間になっています。
どうして、こうなのか?と次々に疑問が湧いて出ます。どのようにして考えが生まれ、
また消化され最終的に「ひとつ」にまとまって行くのか、とても興味があります。
こんなものを作ってみたい。シンプルにそう思いました。それまでの自分がやってきた
芸術活動を、ひとつにすることが出来ると思ったからです。絵画でも写真でも
彫刻でも音楽でも融合させることが出来るのが建築だと思い込みました。
だから私は建築が儲かる、建築で就職できる、建築士の資格で安定した生活が
出来るという発想は「ただのひとつ」も持たないで「突然」、設計の仕事を始めました。
勉強と同時に仕事をしだしたのです。今思えば、なんという無謀な行為。
それを息子に知って欲しかったのです。
息子は石の教会に入ると黙ったまま、いつまでもいつまでも建物の中を見つめて
いました。その多くの視線は天井に向けられていました。それこそが、ケロッグが
目論んでいた空間構成の意義だったと私は思いました。神は天から私たちを
見守っておられます。天井から降り注ぐ光や風、熱は神の存在を意識する大切な
ファクターです。それらの存在を最も感じられる状態に組み立てた力量は、
手放しに敬意を払うに値すると私は思っています。
大学に行って何を掴んで帰ってくるのか。それは様々でしょう。どの大学でも
人の運命と「宿命」について変えてしまうほどの出会いは無いでしょう。どこでも
同じ気がします。ただ息子に「人の評判」「他人の価値観」で自分の思い描いた
建築家への夢の扉を開いて欲しく無かったのです。
帰りの車中で色々話をしました。息子の言葉数は少なかったです。深く何かを
考えているようでした。自分の三年間を振り返っていたんだと思いました。
「もしも」という話ほど、つまらない「例え」は無いです。人の人生は、ひとつで命も
ひとつしかないのですから。選択が有ったとしても、選択した瞬間には、もうひとつの
選択肢は消えてなくなるのです。三年前に志望校を、もっと偏差値の低い簡単な
大学にしていたら、この三年間「缶詰」になって孤独に家で勉強をしていなかった
かもしれないと思えば、心は押しつぶされそうになると思います。
そして結果、自分が思い描いた結末には、とうとうならなかったのですから。
私は、とても流暢には自分の想いを息子に話すことは出来ませんでした。
話していると泣いてしまいます。途切れ途切れになった言葉を、しっかりと息子に
伝えようと、それでも話し続けました。この三年間の貴重な体験は息子の「その後」の
人生に計り知れないほどの「福音」をもたらすはずです。多くの人が、そう言う筈です。
しかし今この瞬間に、その言葉は「ただの詭弁」にしかならないだろうということにも
多くの人が気が付くはずです。人生は断続的に発生する訳ではありません。
この三年間があったからこそ今が存在しているのです。今の息子がいるのです。
何度も言いますが、信大の合格発表前なのに日大と、どっちに行くかって話しを
しているのですから、馬鹿な親子です(笑)
結論は出ずにいました。当然です。信大の合格発表前であり、早稲田の補欠の
発表前でしたから。この時点で親子ともども受かっていれば早稲田に入学する
つもりでいたと思います。ただ息子は物凄い学費に、行きたいとは一度も口にする
ことはありませんでした。私は学費は、なんとかするつもりでしたが、補欠で合格できる
可能性は「無いに等しい」と考えていたので、これ以上傷つきたくないという気持ちから
早稲田への進学については口にしませんでした。3月19日、早稲田の補欠合格発表が
ありました。残念ながら息子は不合格でした。息子は「まぁ駄目だと思ってたけど」
「ちくしょー、補欠、出たのかなあー」と笑いながら叫んでいましたが、心の片隅で
受かっていて欲しい、そうすれば悩みが消えるんだと考えていたでしょう。そう映りました。
翌20日。信大の合格発表が有りました。合格です。合格通知を受け取った息子の
表情は浮きませんでした。前橋工科大学のときと似ています。やはり後期試験とは、
こういうポジションなのかと複雑な気持ちになりました。中堅の国立大学の、しかも
後期試験という大変な狭き門で合格したのに、浮かない気持ちになるとは、他の
受験生の方には大変に申し訳ない気持ちになりました。息子も同じだったと思います。
この合格発表を聞く前に息子は「日大に行こうかな」と小さな声で言ったことがありました。
兄弟からも「お前、日大に行くんだろ!!」とはやされても「まだわかんねーだろ」などと
本気なのか冗談なのか分からないような口論をしていました。私は、じっと待つしか
ありませんでした。息子が決めるのを。
ただ。息子には学費は心配するな、ちゃんと用意できる。一人暮らしも、ちゃんと
出来るように用意して有ると何度も言いました。嘘です。この時点で二次の入学金の
用意すらままならない状態でした。息子に金のことで私学を諦め、ただ安いという理由
だけで国立大学を選ぶようなことだけは「親として」避けて欲しいと、建築家ではなく、
どこにでもいる「一人の親」として、してあげられる最後の仕事だと思っていました。
日大の振込みの最終日は25日でした。24日に最後の意思確認を息子にしました。
「俺、日大が良いな。日大に行きたい」と力強く答えました。嬉しかったです。
現役から数えれば4年間も偏差値にだけ振り回されて、やたらに勉強の出来る子供に
なることが出来ました(笑)もしかすると成績上位者になって奨学金も貰えるかもしれないし、
それは、それで良かったと思います。この2年間で少しだけ建築の専門的な知識も
教えることも出来ましたし、なによりも日大理工建築という名門を息子が理解してくれた
ことに喜びを感じます。理工建築の学生は、1学年で300人近くになります。これに工学部の
建築や他の建築を学べる学科を合わせると、とんでもない数の生徒数になります。
理工建築だけでも300人です。意匠設計に特化した研究室は、三つです。
これは狭き門です。自分から学ぶ姿勢、掴みに行く姿勢が育たなければ、マンモス大学で
有意義な学生生活など送れるはずが、ありません。学生生活を楽しんで欲しいという親心も
ありますが、果たして建築学科の生徒にそのような「のんきな」時間を過ごす、ゆとりなど
有るものでしょうか。折角、建築の勉強を始められるのです。貪欲に建築を探っていって
欲しいと思います。
おめでとう響。お前は自慢の息子だよ。本当に立派だと思う。尊敬すらしているよ。
ありがとう。俺の子供に生まれてきてくれて。

早稲田大学の補欠の発表が終わって、信州大学と日大と、
どちらの学校に入学するのが良いのだろうと「親目線」で
真剣に考えるようになりました。決して、この時点では
「建築家」としてでは有りませんでした。
息子の気持ちを最優先に考えていました。学校に通うのは
当の本人ですから。当たり前のことです。
ネットの情報を死ぬほど漁りました。中々結論が導き
出せなかったからです。それは昨日の記事にも書いたように
「思い込み」は大きく間違った選択をする危険が有るという
ことを嫌という程知ったからです。
息子の高校受験のときに偏差値の高い順に「良い学校」だと
妄信的になっていて、この学校に入れば「良い大学」に入れる
だろうと、馬鹿なことを考えていました。あながち全く間違った
考えではないのですが、受験というよりも「勉強」なんてものは、
「本人次第」な訳です。少々厳しく課題を出されたりした程度では、
とても学力なんて定着しません。逆に宿題を山ほど出しておいて、
ろくに提出物に対して評価や指導をしない学校では自分の
時間が取れなくて学力は低下するはずです。それに進学校
なのにムキニなって部活をやらせるのも子供たちには負担に
なるはずです。得られるものも多いでしょうけれど「失うもの」が
れっきとして存在することを肝に銘じておいて欲しいです。
息子の通った学校は正に、そのような学校でした。
入学したばかりのときは、いわゆるトップ校との差は僅差という
より「ほぼ無い」という状態の成績の子供たちばかりなのに、
卒業する頃には、その差は簡単には埋められないほどの
実力差になってしまっています。息子は遠距離の通学という
ことも有って、部活は文化部。いわゆる帰宅部でしたが、通学に
時間をとられて、宿題も深夜まで掛かってやっていました。
このガッツは、トップ校の生徒に負けたくないという「意地」でも
あったと今は思っています。御蔭で成績は好ましい状態でしたが、
所詮は校内の成績です。2年生くらいまでの模試でも志望校の
合格判定はA、Bを出していましたが、早すぎる模試の結果は、
丸で当てになりません。
現役のときに受けたセンター試験の結果を「合格判定システム」に
掛けて、担任の先生は「矢継ぎ早に」「ここはどう?こっちはどう?」
などと、丸でユニクロにフリースでも買いに行ったように「適当に」
偏差値だけで合格しそうな大学が記載された紙をベラベラと
息子と私の前で何枚も出し続けたのでした。これが「進路指導」です。
呆れました。全く信頼できませんでした。
入学したときのガイダンスでは男性教諭が「私の息子は静高に
通っていますが、進路相談なんて全くしてくれませんよ」「東校は
本当に親身になってやっていますから、良い学校に入学されました」と
堂々と言ってのけていました。
その静岡高校も浪人生ばかりを大量に排出しています。大変に
自由で私は好きですね(笑)実は大抵の家庭の親御さんも、
お子さんの進学先を「適当」に決めているのではないかと思います。
私のように大学受験の経験も無ければ尚更だと思います。
私の場合「自由」を最も大切にしていますから、基本的には
「子供の自主性」に任せています。悪い言い方をすれば「勝手に」
すれば良いということでしょうか。ただ、私は、そういった「そぶり」は
見せていますが、ちゃんとバックアップを取っておくということに、
相当に気を使っています。そうです子供の選択が妥当かどうかです。
正しい、間違っているではありません。
現役のときに受けた千葉大学は良い仕事をしている建築家が結構
出ていると認識がありました。私は最近相当に評判の良い
横浜国立大学の建築コースを出られて、仕事に恵まれた建築家を
余り知らなかったので、わざわざ大変な思いをして「偏差値」に拘って
受験することもないと子供には言いました。話に聞くと新しい情報では
横国の教授には相当な方がいらっしゃるとか。また設備も日本一くらいの
レベルだそうで、人気が高いのも頷けるという状態らしいです。
建築というか、建築設計の世界の中にいると、やはり東大を出た
建築家の仕事は「羨望」の的だと感じます。強がりを言ってみても、
やはり「こんな仕事をしてみたい」と思わない能力の高い建築家は、
いないでしょう。東大を出ているということは設計の能力とは全く関係の
無いところで「別の」チャンスをもたらせてくれるのは事実です。
では東大が無理だったら次は「どの大学」でしょう。
多くの受験生は「そこが」気になるのです。毎年大勢の建築家志望の
子供たちが大学を受験します。様々な境遇に有ります。
話を戻します。
大学に行く意味を改めて私は考えてみました。私は独立当初から
海外の設計コンペに挑戦して来ました。海外の設計コンペは「All」と
書かれているものが多いです。つまり誰でも参加できるということです。
出身大学というか、資格さえ問われないことが多いのです。
それは建築を芸術だと捉えている部分が大きく影響していると思います。
勿論、大規模建築物には建築の専門的な知識や要素が有って、初めて
成り立ちます。いや小規模な家や小屋でさえそうです。
ですから誰でも提案できるといっても、当然それらが、
ちゃんと成立していなければコンペで勝つことは出来ません。
従ってデザインやコンセプトなど「独自性」のあるものは自ら創造できても、
それに付随する知識や能力、また「判断力」「判断材料」を学ぶために
大学に進学することが息子には必要であり、有意義な時間と金の
使い方だと結論付けたのです。
今更ですが「大学」ではなくて「誰が」私の息子に建築を教えてくれるのか?
が最も大切だと気が付いたのです。調べました。
信大の工学部建築学科は「たったの59人」しか合格できません。
前期で44人後期で15人。後期の倍率は9.9倍です。大変に狭き門です。
10人に一人しか合格できません。どうしてこんなにも大勢の受験生が
殺到するのでしょうか。考えました。
国立大学といえば誰もが知っているように「学費」が安いことが上げられます。
大学を選ぶときに当然「受かりそう」な大学を選ぶ訳ですが、
偏差値が中間に近づくにつれて構成する人口も増える訳ですから、
当然激戦になる訳です。出来るだけ安い学費で済ませたいと考えるのは
人情でしょう。成績の優秀な子供たちが多く合格して行くのは必然です。
このことから国立大学は優秀な生徒が集まる。国立大学は良い大学だと
認知されているのだと思います。間違ってはいません。さて私が信大の
工学部建築学科を調べた結果ですが、意匠の研究室は、一つだけしか
ありません。デザインや設計の専門科目の授業も少し少ないなと感じました。
印象としては「工学部」だなぁという感じです。当たり前の話ですが、
工学部では工学的な勉強をします。東大や京大など旧帝大や国立大学の
多くは「工学部」の中の建築学科です。つまり建築の研究をするというよりは、
社会で役に立つ技術の習得が「まずは」第一目標になっている訳です。
そうは言っても、やはり建築家の養成をするクラスも有るわけです。
東大などは、やっとこ3年生になってから本格的に建築を勉強する訳ですが、
下手をすると成績によっては全く違う学科に追いやられてしまうのです。
これは他の大学でもそうです。仮にデザイン寄りの勉強をしたくても、
設計の成績が悪ければ構造や計画などの教室に振り分けられてしまいます。
それでも意匠設計のクラスが多くあればチャンスは広がります。もっとも
生徒数が多ければ比例してクラスが多くなるというだけで、果たして
60人の生徒と300人の生徒では5倍のクラスが、なければ平等とは
言えませんが、やはり教授の質には関心が残ります。
信大で刺激的な4年間が送れるのか。物凄く気になりました。
それは勿論、本人次第なのですが、クラスメートや教授に影響される部分は、
相当に有ると思うのです。
私立大学と授業料を比べると軽く年間で100万円を超えるほど差もあります。
どんなに早稲田の建築が良くても東工大に受かったら、そちらに進学する
のだろうと思います。普通の考え方です。それでも早稲田の建築は
日本一人気の有る大学です。多くは「就職に有利」だからだと言われます。
ですが、この就職については、余程の大学でもなければ大差の無い就職先で、
日大理工の就職率は97%以上です。理科大も芝工も立派なものです。
それでも東大、京大、早稲田の人気が高いのは、やはり「偏差値」で
学校を選んでいるからだと思うのです。正直、東大と早稲田の建築学科は、
魅力的なカリキュラムです。プロの私から見ても、最先端を意識して
学生達を切磋琢磨させていると、はっきりと目に映ります。
もしかすると偏差値の低い学校では、ろくに勉強もしない、態度の悪い
生徒もいて、ゼミの雰囲気を悪くしているのでは、ないだろうかと心配に
なっている受験生や親御さんが多くいるのではないかと想像します。
私も心配しました。だからきっと偏差値の高い難関大学は信頼されている
のだと思うのです。でも今語っている「偏差値」について、一概に唯一の
判断材料として良いかどうか、先程らい語っているように危険ですらあると
私は気が付いたのです。それを息子に話しました。
ええ、信大の合格発表前なのにです。馬鹿げた話なのですが、正直、信大は
絶対に受かっていると思っていました。受ける前からです。早稲田が補欠に
なった時点で、京大の結果も、そんなに悪くなかっただろうと想像しました。
偏差値で行けば早稲田も京大の建築も同じくらいです。補欠者は40人程度
でしたから合格者との点差は10点も20点もあった訳ではありません。
もしかすると1点差が有るかどうかってことだって有り得ます。そこから
判断するに信大の後期の偏差値は越えていたと考えたからです。
長野市に向かう車中で家内に私の考えを話しました。これは根拠に乏しい
ような持論を含めてです。反論を承知で書きます。あくまで持論です。
日本で建築を勉強するなら、やはり東京が一番良いと思います。
なぜなら名建築が山のように在るからです。本の中で見た気になる建築を
自分の目で簡単に見に行くことが出来ます。オープンデスクでも、
入れてもらえるか、どうかは、さておいても、聞いた事の有る名前の
建築家の設計事務所を訪ねて行くことが出来るのです。学校や研究室を
超えて、繋がって刺激し合い、洗練されて行くことが出来ると感じるからです。
私は信大に合格できても日大に行った方が良いと思いました。
家内も同意しました。
試験を終えたばかりの息子に今まで相当に研究し、また考察した私の結果を
「勇気」を出して伝えました。勇気が必要になったのは、それが「日大」だからです。
私たちの年代ですと日大は「日東駒専」と、ひとくくりにされて、あたかも
誰でも入れるような馬鹿大学だと揶揄されていたことを知っているからです。
そして現在でも、その馬鹿馬鹿しい偏差値偏重のせいで多くの受験生が、
間違った学校選びをしていると感じます。日大と一口に言っても医学部に
始まって、学部によって難易度の差は大変に大きいです。
その中でも理工建築学科は決して簡単に合格できるような学部ではありません。
我々建築に携わる人間にとってみれば日本の建築学部と言ったら、
東大、早稲田、日大理工です。
近いところで単科大学なら芝浦工業大学の建築学科も大変に優秀な学生が
多く、卒業生も素晴らしい活躍をされている方が物凄く多いです。
息子は大変に「大人しい」性格です。本当は信州大学のキャンパスの雰囲気の方が
合っていると思います。信大にいそうです(笑)でも冗談抜きにプリツカーを狙える
だけの建築家になりたいのなら、やはり刺激を受けて海外のアトリエに
勤めて欲しいと思います。もう甘えて生きる期間は終わったんだと思います。
親としては心配が増えるだけなのですが、泣いてばかりは、いられません。
息子には「これが俺の考えだ。でも行くのは、お前だ。自分で考えて結論を出せ」
そう言いました。そして私の考えを目に見える形で記憶してもらおうと、帰路を
逸れて軽井沢に向かいました。
私が建築家を志そうと決意した建築を見せたかったからです。
軽井沢高原教会です。
私たち夫婦が結婚式を挙げた教会です。ここには「ふたつの礼拝堂」があります。
私たちが挙式を上げたのは通称「木の教会」でしたが、隣接するもう一つの
礼拝堂、通称「石の教会」を、どうしても息子に見せたかったのです。
軽井沢は遠かったのですが、この機会を逃しては二度と「三人」で来ることは
叶わないだろうと思って強行しました。私たちが結婚式を挙げたときには家内の
お腹には息子が宿っていました。ですから三人で再び訪れたのは22年ぶりという
ことになります。実に感動的でした。
息子は常々私が語っているので石の教会については知っていました。
でも写真を見ただけでは、この建築物が存在する本当の意味は、ひとつも伝わらない
だろうと私は考えていたからです。石の教会は、ケンドリック・ケロッグという
アメリカ人の建築家の設計によるものです。とても特徴の有る設計をする人で、
もっともっと有名になっても良いと思うのですが、近くで教会を実施した
レーモンド程知名度はありません。私は初めて、この教会を見たときに建築物を
見ているというよりも「空間」や「成り立ち」「思想」を目で眺めることが出来るもの
なんだと深く深く感動したのを昨日の事のように覚えています。わざわざ言われなければ、
これが教会なんだとは誰の目にも映らないでしょう。内部の写真撮影は禁止されて
いるので、内部を紹介された資料は、とても少ないです。
建物の「奇異」さだけが印象に残ってしまうので、星野リゾートには、もっと内部の
画像の公開を望みたいです。内部は外観よりも更に異空間になっています。
どうして、こうなのか?と次々に疑問が湧いて出ます。どのようにして考えが生まれ、
また消化され最終的に「ひとつ」にまとまって行くのか、とても興味があります。
こんなものを作ってみたい。シンプルにそう思いました。それまでの自分がやってきた
芸術活動を、ひとつにすることが出来ると思ったからです。絵画でも写真でも
彫刻でも音楽でも融合させることが出来るのが建築だと思い込みました。
だから私は建築が儲かる、建築で就職できる、建築士の資格で安定した生活が
出来るという発想は「ただのひとつ」も持たないで「突然」、設計の仕事を始めました。
勉強と同時に仕事をしだしたのです。今思えば、なんという無謀な行為。
それを息子に知って欲しかったのです。
息子は石の教会に入ると黙ったまま、いつまでもいつまでも建物の中を見つめて
いました。その多くの視線は天井に向けられていました。それこそが、ケロッグが
目論んでいた空間構成の意義だったと私は思いました。神は天から私たちを
見守っておられます。天井から降り注ぐ光や風、熱は神の存在を意識する大切な
ファクターです。それらの存在を最も感じられる状態に組み立てた力量は、
手放しに敬意を払うに値すると私は思っています。
大学に行って何を掴んで帰ってくるのか。それは様々でしょう。どの大学でも
人の運命と「宿命」について変えてしまうほどの出会いは無いでしょう。どこでも
同じ気がします。ただ息子に「人の評判」「他人の価値観」で自分の思い描いた
建築家への夢の扉を開いて欲しく無かったのです。
帰りの車中で色々話をしました。息子の言葉数は少なかったです。深く何かを
考えているようでした。自分の三年間を振り返っていたんだと思いました。
「もしも」という話ほど、つまらない「例え」は無いです。人の人生は、ひとつで命も
ひとつしかないのですから。選択が有ったとしても、選択した瞬間には、もうひとつの
選択肢は消えてなくなるのです。三年前に志望校を、もっと偏差値の低い簡単な
大学にしていたら、この三年間「缶詰」になって孤独に家で勉強をしていなかった
かもしれないと思えば、心は押しつぶされそうになると思います。
そして結果、自分が思い描いた結末には、とうとうならなかったのですから。
私は、とても流暢には自分の想いを息子に話すことは出来ませんでした。
話していると泣いてしまいます。途切れ途切れになった言葉を、しっかりと息子に
伝えようと、それでも話し続けました。この三年間の貴重な体験は息子の「その後」の
人生に計り知れないほどの「福音」をもたらすはずです。多くの人が、そう言う筈です。
しかし今この瞬間に、その言葉は「ただの詭弁」にしかならないだろうということにも
多くの人が気が付くはずです。人生は断続的に発生する訳ではありません。
この三年間があったからこそ今が存在しているのです。今の息子がいるのです。
何度も言いますが、信大の合格発表前なのに日大と、どっちに行くかって話しを
しているのですから、馬鹿な親子です(笑)
結論は出ずにいました。当然です。信大の合格発表前であり、早稲田の補欠の
発表前でしたから。この時点で親子ともども受かっていれば早稲田に入学する
つもりでいたと思います。ただ息子は物凄い学費に、行きたいとは一度も口にする
ことはありませんでした。私は学費は、なんとかするつもりでしたが、補欠で合格できる
可能性は「無いに等しい」と考えていたので、これ以上傷つきたくないという気持ちから
早稲田への進学については口にしませんでした。3月19日、早稲田の補欠合格発表が
ありました。残念ながら息子は不合格でした。息子は「まぁ駄目だと思ってたけど」
「ちくしょー、補欠、出たのかなあー」と笑いながら叫んでいましたが、心の片隅で
受かっていて欲しい、そうすれば悩みが消えるんだと考えていたでしょう。そう映りました。
翌20日。信大の合格発表が有りました。合格です。合格通知を受け取った息子の
表情は浮きませんでした。前橋工科大学のときと似ています。やはり後期試験とは、
こういうポジションなのかと複雑な気持ちになりました。中堅の国立大学の、しかも
後期試験という大変な狭き門で合格したのに、浮かない気持ちになるとは、他の
受験生の方には大変に申し訳ない気持ちになりました。息子も同じだったと思います。
この合格発表を聞く前に息子は「日大に行こうかな」と小さな声で言ったことがありました。
兄弟からも「お前、日大に行くんだろ!!」とはやされても「まだわかんねーだろ」などと
本気なのか冗談なのか分からないような口論をしていました。私は、じっと待つしか
ありませんでした。息子が決めるのを。
ただ。息子には学費は心配するな、ちゃんと用意できる。一人暮らしも、ちゃんと
出来るように用意して有ると何度も言いました。嘘です。この時点で二次の入学金の
用意すらままならない状態でした。息子に金のことで私学を諦め、ただ安いという理由
だけで国立大学を選ぶようなことだけは「親として」避けて欲しいと、建築家ではなく、
どこにでもいる「一人の親」として、してあげられる最後の仕事だと思っていました。
日大の振込みの最終日は25日でした。24日に最後の意思確認を息子にしました。
「俺、日大が良いな。日大に行きたい」と力強く答えました。嬉しかったです。
現役から数えれば4年間も偏差値にだけ振り回されて、やたらに勉強の出来る子供に
なることが出来ました(笑)もしかすると成績上位者になって奨学金も貰えるかもしれないし、
それは、それで良かったと思います。この2年間で少しだけ建築の専門的な知識も
教えることも出来ましたし、なによりも日大理工建築という名門を息子が理解してくれた
ことに喜びを感じます。理工建築の学生は、1学年で300人近くになります。これに工学部の
建築や他の建築を学べる学科を合わせると、とんでもない数の生徒数になります。
理工建築だけでも300人です。意匠設計に特化した研究室は、三つです。
これは狭き門です。自分から学ぶ姿勢、掴みに行く姿勢が育たなければ、マンモス大学で
有意義な学生生活など送れるはずが、ありません。学生生活を楽しんで欲しいという親心も
ありますが、果たして建築学科の生徒にそのような「のんきな」時間を過ごす、ゆとりなど
有るものでしょうか。折角、建築の勉強を始められるのです。貪欲に建築を探っていって
欲しいと思います。
おめでとう響。お前は自慢の息子だよ。本当に立派だと思う。尊敬すらしているよ。
ありがとう。俺の子供に生まれてきてくれて。

2019年04月03日
巣立ち
一昨日、長男が家を出て行きました。
毎日、四六時中、泣いています。こんなにも辛いのかと。
息子の名前を口にする度に涙が出ます。
長男に次いで次男も今週末には出て行きます。
非常に辛いです。子供たちが幼かった頃の姿が、
ひっきりなしに目に浮かんできます。楽しかった思い出しか
蘇ってきません。私が至らなかったことも沢山思い出します。
子供たちに、もっとこうするべきだったと。ずっと謝り続けて
います。子供たちの御蔭で本当に勉強させてもらいました。
本当に豊かな人生だったと思います。華のある毎日でした。
長男は三浪の末に「やっと」大学生になります。
ありがたいことに現役で前橋工科大学の工学部建築学科の
後期試験で合格したのですが、入学は辞退しました。
息子は、所謂「勉強の出来る子」でした。中学校の頃から
成績は優秀で、入学したときから卒業まで、ずっとトップ
でした。しかし志望していた高校は受験できませんでした。
静岡県は、まだまだ「公立高校」至上主義で、私立高校の
進学コースなどは、進学先として検討するときに2番目に
なっているのが現状です。担任の先生から落ちたときに進む
私立高校の授業料などを鑑みて、我が家には負担が大きい、
ランクを落として公立高校を受験するべきだと指導され続けた
結果、自ら選択して志望校を決定しました。難関高校です。
十分、立派な学校でしたから親も息子も納得していました。
と、思っていたのですが、そうでもなかったと息子の口から
聞いたのは、なんと4日前のことでした。驚きました。
息子は、やはり「偏差値」の1番高い地元の公立高校を
受験したかったけど2番目の学校にしたのは若干悔いが残った
と私に言いました。私もなんとなく、そうだろうと思っていました。
ですが、高校の選択で誤ったこと学んだことが大学受験で
生かされるようにと考えていました。でも更に間違うことに
なったのかもしれません。
前橋工科大学を辞退した理由は明確です。
「偏差値が低い学校」だったからです。息子は建築家を
目指していました。もちろん漠然とです。父親が建築家なので、
建築家に漠然と憧れただけです。子供なんて、そんなものです。
高校に入った当初から志望校は「東京工業大学」だったそうです。
東工大は知る人ぞ知る名門大学、超難関大学です。工学系の
単科大学では日本一入るのが難しい大学です。偏差値も東大の
理科Ⅰ類と肩を並べるくらい高い大学です。
息子は「リベンジ」をしたかったんだと思います。単純に「東大」は
無理だろうから、東大を除いた最難関大学に受かってやろうという
理由で「目標」を設定していたんだと思います。
事実、高校に進学してからも成績は上位で優秀でした。
ですが、3年生になると自分よりも、ずっと下の成績だった同級生に
ガンガン追い越されるようになりました。模試の結果も良い結果
ではありませんでした。あまりにも理科の実力が低くて、東工大に
現役で合格する可能性は、ほとんど無いと受け取っていました。
息子に受験校選択で相談されたとき、本当に建築を学びたいのかを
尋ねました。その決意だけは全く変わらないことを確認して、
私の持論を息子に伝えました。正直、建築家、つまり「意匠設計」を
生業にしたいのならば東工大は「的外れ」な気がすると言いました。
本日の記事を書くに当たって、相当に「ためらい」が有りました。
正直3年前から、いつか「この記事」を書く日が来るんだなと「構えて」
いました。書きにくい内容ばかりです。それでも受験生や、
その親御さんが、この記事に辿り着き、進学先で悩んでいる状態に
解決の糸口を見つけられるならばと思い、書き記しています。
東工大の6類、つまり建築学部が悪い大学な訳がありません。
息子が受かったのなら小躍りして喜びます。
話を戻します。結局現役の時には、センター試験の結果が思わしく
無かったので、二次試験の比率が高い大学で建築を幅広く学べる
環境にある大学を受験しました。千葉大学です。千葉大学の建築学科は
難関です。息子のセンターの結果は7割を切っていました。正直、
国立大学の前期試験で7割を切った結果で合格するには、相当に
二次力が無ければ無理です。結果は合格には程遠い点数でした。
前橋工科大学を辞退した理由には、もうひとつ有ると思います。
後期試験では「小論文」だけだったからです。つまりセンターの結果が、
殆どだったということです。よくある合格判定システムなどの利用では
「C判定」でしたが、合格できました。運が良かったのかもしれません。
ただ、息子は一生懸命に勉強をしてきて、作文ではなく「学んだ」
学問で評価をして欲しかったと考えたようです。前橋工科大学の
4年を経てからの進路は地元工務店や「他大学の大学院」が多いようです。
つまり学士だけでは「寂しい」と感じている学生が多くいるのではと
推測しました。本気で建築を学びたいのであれば、少々不満が残る
かもしれないと伝えました。それが先ほどにも書いたように、息子の
「もっと難しい大学」への憧れに繋がって行ったのかもしれません。
一浪目は本当に死ぬほど勉強をしていました。経済的にも時間的にも
予備校に通うのは難しい、そして何より「自分で納得する」まで勉強を
する息子には「宅浪」が合っていると思いました。宅浪は大変だという
声を沢山耳にします。カナリ心配をしましたが、なにより息子が気持ちを
切り替え「東京大学」を目指すという姿勢で、さっさと勉強を開始した
姿を見て、親としては応援するしかないと腹をくくりました。
息子が東大を目指すことにした理由は私の言葉も大きかったと思います。
「お前、アスペルガーだから、東大ならイケルんじゃね?」です。
東大には、アスペルガー症候群の生徒が多く通っていることで有名です。
アスペルガー症候群は特異な性質を持っています。息子の症状は
顕著ではありませんが、やはり「普通」とは違う「才能」を感じます。
私は冗談半分でしたが息子が、いわゆる「普通の人生」を歩んで行く
というビジョンが見えなかったのです。これについては今でも疑っていません。
ただ実際には模試の結果は、殆どがE判定。思いつきで受かるような
大学ではありません。ただ。私は上に向かって投げたボールは放物線を
描いて落下するものだと考えていました。高い目標を持てば、
いや持たなければ現役と同じ結果になると考えてもいました。
この年もセンターで失敗しました。結果は7割を超えた程度でした。
二次の勉強ばかりをして、社会や国語の結果が振るいませんでした。
で、現役当時の目標であった東工大を受験することになりました。
併願校は早稲田大学の創造理工学部建築学科です。どちらも同じくらいの
偏差値で、どっちが簡単に受かるという学校ではありません。
一年鍛えた成果を試すには不足の無い学校でした。ですが、この2校とも
合格には程遠い試験結果でした。この年は国立の後期試験では
名古屋工業大学の建築学科を受験しましたが、結果的に全落ちでした。
名工大の試験では「受かった」くらいの手ごたえが有ったようですが、他の
受験生の結果も相当に良かったということです。名古屋大学を落ちたような
センターの結果が良かった受験生が多く受けている傾向が有るようです。
二次の問題も難易度が高く、しっかりと点数を取っておかないと、
後期で合格することは難しいようでした。
この年は「滑り止め」なる学校は1校も受けませんでした。全落ちした息子の
狼狽は半端無い状態でした。流石に私も泣けてきました。後期の不合格が
決まった日には息子と「ひとつ」の布団で寝ました。守ってあげたい。
ただただ、そう思った日でした。
二浪が決定して、前年よりも比較的ゆっくりとした浪人生活が始まりました。
放心状態です。また東大受験の日々のスタートです。模試の結果は、
前年よりは上がっていますが、やはり最高でもC判定。夏休み頃になると
現役の受験生達も力をつけてきて息子の力不足が浮き彫りになります。
私は息子に様子を聞きました。息子は「東大の試験は物凄いスピードが
要求される。それも正確に物凄い量をこなさなければならない。」
「時間が有れば解けるけど、俺には難しい」と零してきました。
私は、だったらじっくり考えさせてくれる東工大や京大の方が良いんじゃ
ないかと息子に言いました。結局、この年もセンターの結果が8割をやっと
超えた程度だったので、東大は諦め京都大学を受験することになったのです。
それでも日本一難しい大学であることは間違いありません。東大と京大では
受験の傾向が違っていますので大慌てで京大の受験対策をすることになった
のでした。この年も併願校は早稲田大学でした。それから流石に、もう浪人は
出来ないといういことで「滑り止め」を受験することを強く勧めたのですが、
息子は真剣に私学の偏差値の低い学校の受験を考えようとしませんでした。
分かる気がします。現役のときに、わざわざ辞退して難関大学の合格に
拘ったのですから。二浪までして今更考えてもいない大学に通えるかという
気持ちなんでしょう。この頃やっと私は父親として、建築家としての持論を
息子に細かく話すようになりました。
正直、建築を学ぶのなら偏差値は、ほぼほぼ当てにはなりません。恐らく。
私は高卒ですし、そもそも学校で建築学を教わっていませんから、大学での
建築の勉強が「どれくらい有意義」なのか正確に判断できません。
でも企業に就職をして会社員として働きたいという希望ならば、それは有名な
大学で優秀な成績を収めれば有利になると思います。東大や京大、早稲田を
優秀な成績で卒業すれば、まず間違いなく一流企業に就職できます。
でも建築家になりたいのなら、そこからの「進む道」と在学中に得た「知識」で
大きく進路は変わってくると思います。
何処の大学だって建築を学ぶ内容は大差ありません。1級建築士の資格を
取得することが最終目標のような大学では、建築の一部しか触れることが
出来ないと思います。資格が無ければ働けないような環境に就職するのならば、
そういったことに力を入れている大学を選べば良いです。そうなってくると東大や
京大、早稲田大学は的外れな選択となるでしょう。
こういった話をした結果、息子は日本大学の理工学部建築学科に
「センター利用」で出願しました。完全に日東駒専を舐めていましたね。
ろくなリサーチもしないで出願しました。勿論出願は、センター試験前なのですが、
8割を超えた結果に流石に親の私も受かっているだろうと思っていました。
ですが結果は不合格。背筋が伸びた状態で早稲田の受験、京大の受験と
なりましたが、結果この年も全落ち。息子の様子を直視できませんでした。
ですが、三浪に突入したときは今までと違い浪人生活を楽しむような気配すら
感じられました。勉強が楽しくなってきたのでしょう。息子は言っていました。
高校生のときに化学の授業が全く分からなかった。何を言っているんだろうという
くらい、全く理解できなかったと。息子は独学で化学を習得しました。
地味に教科書やチャートを解き、有名で高度な参考書や問題集を解いたのです。
最初は相当に苦しんだようです。でも記念受験では無く、本気で京大を
受けて合格しようとするだけの「力」のようなものを自分でも持っていると感じて
いたのでしょう。
相変わらず模試の結果はC、B判定止まりでしたが、安定していたので
私の眼からも今年は、いけるかもしれないと感じていました。今回は流石に
リサーチも十分して滑り止めには工学院大学の建築学科をセンター利用で受験
しました。今回のセンターの結果は8割を越えましたが、わずかに8.5割を
下回ってしまいました。 なんとか京大の合格最低レベルくらいです。
日大理工建築のセンター利用の合格ボーダーは8.5割です。一般で受けることに
しておいて良かったです。というか、センター利用で合格できる中堅以上の
私立大学は「滑り止め」のような受験校には成り得ないと感じました。
工学院の合格、そして日大の合格は気持ちに、ゆとりが出来、本命の
早稲田、京大の受験に弾みがつきました。この時点で息子は私立大学に
進むつもりは持っていなかったようです。やはり私大は、お金が掛かります。
文句なしの名門であり、学費も抑えられ「リベンジ」も果たせる、三浪の苦労を
吹き飛ばすことの出来る京大の入試こそ自分の大本命だと位置づけていたと
思います。早稲田の受験後の印象では「微妙」だと言っていました。
でも、それまでの感想とは大分違っていました。全く出来なかったという表情では
なかったのを良く覚えています。京大の受験には同行しました。
相当に力んでいました。初日の英語で失敗してしまったようです。完全に
パニックになったと言っていました。それでも去年は結果的に「ゼロ完」だった
数学も「3完」出来たし、本人も手ごたえを感じていたようでした。京大の
試験2日目が早稲田の合格発表でした。私は清水寺にやっと辿り着いた
広場でネットの発表を見ました。息子の受験番号は有りませんでした。
「補欠」にも有りませんでした。物凄い喪失感でした。それでも御本尊様に
手を合わせないで帰る訳にはいかないと、自分を奮い立たせ、
なんとか御本尊様に手を合わせて息子を京大まで迎えに行きました。
会うと疲れきった様子でした。「あんまり出来なかったな」と力なく答えました。
私は息子の頑張りを褒め称え、兎に角「あそこのラーメンを食って早く家に帰ろう」
と、去年も帰る際に立ち寄った祇園のラーメン屋に息子と向かいました。
何ともいえない表情でした。駄目だったというものでもなく、自信に満ちたもの
でもなく。疲れてはいましたが、やり切ったという程でもありませんでした。
まだ国立後期試験が残っていましたが「終わった」という表情だった気がします。
息子にとって「京大受験」が全てだったのです。
京大からの帰り道、息子に「早稲田、残念だったな」と話しかけると、
「えっ?そうなんだ。俺、見てなかったから」と。早稲田の合格発表を自分では
見ていなかったのでした。「まぁ駄目だと思ってたけど」と力なく、はにかんだ
笑顔で言われました。私は泣いてしまいそうでした。
帰りの新幹線に乗車して暫くして私は早稲田の合格発表を「見落とし」ている
かもしれないという気持ちと発表の画面を息子に見せたいという複雑な気持ちが
入り混じった状態でサイトを開きました。
補欠者のページをスクロールするも、やはり番号は有りません。何の気なしに
横方向へスライドさせると番号に続きが有りました。「なんだ?!」となりました。
スマホの画面では、ちゃんとファイルが開けないようでした。
左2列に表示された番号のテキストは大きなサイズで、右1列は、随分と小さな
サイズで表記されていました。これは補欠のまた補欠なんだと思いましたが、
番号順に並んでいるだけで、成績順ではないことに直ぐに気が付きました。
その隠れていた小さな番号の中に息子の受験番号を見つけました。
「おい!これ、お前の番号だよな?」と言うと「えっ?!なんであるの?!」と息子。
私が、ちゃんと見なかったからだと謝りました。一瞬で息子の表情は明るくなり
ました。ですが息子は「補欠合格、何人取るのかな。そもそも補欠合格なんて
出るのかな」と半笑いでした。そうなんです。早稲田は補欠合格が全く出ない年も
有れば、補欠全員合格の年も有ります。数年前から政府の指導で合格者が
定員以上にならないような措置を採るように強く指導されています。
今年は1.1倍以上にならないようにと指導されています。ほぼ定員です。
定員は80名。合格者が140名程度。早稲田を滑り止めにしている東大や東工大、
どうかすれば慶応、横国。息子のように遠いところでは京大などに合格した
受験生が辞退すれば繰り上がる訳です。この時点で息子の補欠の順位も
分かりませんし、かえって心臓に悪いです。国立の後期試験を受けることに
なりました。正直、私としては早稲田が受かっていれば国立の後期試験は
受けさせないつもりでした。しかし結果は不合格でした。
息子も私も心のどこかで繰り上げに成って欲しいと願っていたと思います。
結果を受けて国立大学の後期試験を受けることになりました。
信州大学の工学部建築学科です。後期は受けないでもと言っていましたが、
私は流石に私立大学の滑り止めに行くくらいなら、しっかりと国立大学を受けて
合格して欲しいと言いました。息子は「どこでもいいな」と願書を提出する時期には
言っていましたが、後期で希望が叶いそうな大学は千葉大学と名工大、
それに京都工芸繊維大学、横浜国立大学辺りでしたが、センターの結果に
自信が無く、横国は無理だろうとなれば、対策の立てようがない千葉大学も
受かる気がしなく、「受かりそう」という理由だけで信州大学を選びました。
以前は小論文だったこともあるようですが、ちゃんと「数学」の試験が課される
ことが息子には合っていると思ったようです。
受験日の前日に長野市に入りました。ひとりで新幹線を乗り継いで行きました。
初めての地で親としては不安でしたが、着いた日には善光寺参りまでして、
落ち着いて受験できたようです。試験が終わる頃に合わせて私は家内と一緒に
自動車で長野まで迎えに行きました。少し考えが有ったからです。
息子と駅で待ち合わせました。「どうだった?」と聞くと
「まぁ思ったより難しかったよ」と息子は答えました。
続けて「まぁ受かったと思うけど」と力なく言いました。大きな失敗もしていないので
例年のボーダーは軽く越えていたと判断したのでしょう。
この時点で息子は信州大学に通うんだろうなと完璧に思い込んでいたと思います。
かなりの長文になりましたが、まだまだ話は終わりません。続きは明日に。
毎日、四六時中、泣いています。こんなにも辛いのかと。
息子の名前を口にする度に涙が出ます。
長男に次いで次男も今週末には出て行きます。
非常に辛いです。子供たちが幼かった頃の姿が、
ひっきりなしに目に浮かんできます。楽しかった思い出しか
蘇ってきません。私が至らなかったことも沢山思い出します。
子供たちに、もっとこうするべきだったと。ずっと謝り続けて
います。子供たちの御蔭で本当に勉強させてもらいました。
本当に豊かな人生だったと思います。華のある毎日でした。
長男は三浪の末に「やっと」大学生になります。
ありがたいことに現役で前橋工科大学の工学部建築学科の
後期試験で合格したのですが、入学は辞退しました。
息子は、所謂「勉強の出来る子」でした。中学校の頃から
成績は優秀で、入学したときから卒業まで、ずっとトップ
でした。しかし志望していた高校は受験できませんでした。
静岡県は、まだまだ「公立高校」至上主義で、私立高校の
進学コースなどは、進学先として検討するときに2番目に
なっているのが現状です。担任の先生から落ちたときに進む
私立高校の授業料などを鑑みて、我が家には負担が大きい、
ランクを落として公立高校を受験するべきだと指導され続けた
結果、自ら選択して志望校を決定しました。難関高校です。
十分、立派な学校でしたから親も息子も納得していました。
と、思っていたのですが、そうでもなかったと息子の口から
聞いたのは、なんと4日前のことでした。驚きました。
息子は、やはり「偏差値」の1番高い地元の公立高校を
受験したかったけど2番目の学校にしたのは若干悔いが残った
と私に言いました。私もなんとなく、そうだろうと思っていました。
ですが、高校の選択で誤ったこと学んだことが大学受験で
生かされるようにと考えていました。でも更に間違うことに
なったのかもしれません。
前橋工科大学を辞退した理由は明確です。
「偏差値が低い学校」だったからです。息子は建築家を
目指していました。もちろん漠然とです。父親が建築家なので、
建築家に漠然と憧れただけです。子供なんて、そんなものです。
高校に入った当初から志望校は「東京工業大学」だったそうです。
東工大は知る人ぞ知る名門大学、超難関大学です。工学系の
単科大学では日本一入るのが難しい大学です。偏差値も東大の
理科Ⅰ類と肩を並べるくらい高い大学です。
息子は「リベンジ」をしたかったんだと思います。単純に「東大」は
無理だろうから、東大を除いた最難関大学に受かってやろうという
理由で「目標」を設定していたんだと思います。
事実、高校に進学してからも成績は上位で優秀でした。
ですが、3年生になると自分よりも、ずっと下の成績だった同級生に
ガンガン追い越されるようになりました。模試の結果も良い結果
ではありませんでした。あまりにも理科の実力が低くて、東工大に
現役で合格する可能性は、ほとんど無いと受け取っていました。
息子に受験校選択で相談されたとき、本当に建築を学びたいのかを
尋ねました。その決意だけは全く変わらないことを確認して、
私の持論を息子に伝えました。正直、建築家、つまり「意匠設計」を
生業にしたいのならば東工大は「的外れ」な気がすると言いました。
本日の記事を書くに当たって、相当に「ためらい」が有りました。
正直3年前から、いつか「この記事」を書く日が来るんだなと「構えて」
いました。書きにくい内容ばかりです。それでも受験生や、
その親御さんが、この記事に辿り着き、進学先で悩んでいる状態に
解決の糸口を見つけられるならばと思い、書き記しています。
東工大の6類、つまり建築学部が悪い大学な訳がありません。
息子が受かったのなら小躍りして喜びます。
話を戻します。結局現役の時には、センター試験の結果が思わしく
無かったので、二次試験の比率が高い大学で建築を幅広く学べる
環境にある大学を受験しました。千葉大学です。千葉大学の建築学科は
難関です。息子のセンターの結果は7割を切っていました。正直、
国立大学の前期試験で7割を切った結果で合格するには、相当に
二次力が無ければ無理です。結果は合格には程遠い点数でした。
前橋工科大学を辞退した理由には、もうひとつ有ると思います。
後期試験では「小論文」だけだったからです。つまりセンターの結果が、
殆どだったということです。よくある合格判定システムなどの利用では
「C判定」でしたが、合格できました。運が良かったのかもしれません。
ただ、息子は一生懸命に勉強をしてきて、作文ではなく「学んだ」
学問で評価をして欲しかったと考えたようです。前橋工科大学の
4年を経てからの進路は地元工務店や「他大学の大学院」が多いようです。
つまり学士だけでは「寂しい」と感じている学生が多くいるのではと
推測しました。本気で建築を学びたいのであれば、少々不満が残る
かもしれないと伝えました。それが先ほどにも書いたように、息子の
「もっと難しい大学」への憧れに繋がって行ったのかもしれません。
一浪目は本当に死ぬほど勉強をしていました。経済的にも時間的にも
予備校に通うのは難しい、そして何より「自分で納得する」まで勉強を
する息子には「宅浪」が合っていると思いました。宅浪は大変だという
声を沢山耳にします。カナリ心配をしましたが、なにより息子が気持ちを
切り替え「東京大学」を目指すという姿勢で、さっさと勉強を開始した
姿を見て、親としては応援するしかないと腹をくくりました。
息子が東大を目指すことにした理由は私の言葉も大きかったと思います。
「お前、アスペルガーだから、東大ならイケルんじゃね?」です。
東大には、アスペルガー症候群の生徒が多く通っていることで有名です。
アスペルガー症候群は特異な性質を持っています。息子の症状は
顕著ではありませんが、やはり「普通」とは違う「才能」を感じます。
私は冗談半分でしたが息子が、いわゆる「普通の人生」を歩んで行く
というビジョンが見えなかったのです。これについては今でも疑っていません。
ただ実際には模試の結果は、殆どがE判定。思いつきで受かるような
大学ではありません。ただ。私は上に向かって投げたボールは放物線を
描いて落下するものだと考えていました。高い目標を持てば、
いや持たなければ現役と同じ結果になると考えてもいました。
この年もセンターで失敗しました。結果は7割を超えた程度でした。
二次の勉強ばかりをして、社会や国語の結果が振るいませんでした。
で、現役当時の目標であった東工大を受験することになりました。
併願校は早稲田大学の創造理工学部建築学科です。どちらも同じくらいの
偏差値で、どっちが簡単に受かるという学校ではありません。
一年鍛えた成果を試すには不足の無い学校でした。ですが、この2校とも
合格には程遠い試験結果でした。この年は国立の後期試験では
名古屋工業大学の建築学科を受験しましたが、結果的に全落ちでした。
名工大の試験では「受かった」くらいの手ごたえが有ったようですが、他の
受験生の結果も相当に良かったということです。名古屋大学を落ちたような
センターの結果が良かった受験生が多く受けている傾向が有るようです。
二次の問題も難易度が高く、しっかりと点数を取っておかないと、
後期で合格することは難しいようでした。
この年は「滑り止め」なる学校は1校も受けませんでした。全落ちした息子の
狼狽は半端無い状態でした。流石に私も泣けてきました。後期の不合格が
決まった日には息子と「ひとつ」の布団で寝ました。守ってあげたい。
ただただ、そう思った日でした。
二浪が決定して、前年よりも比較的ゆっくりとした浪人生活が始まりました。
放心状態です。また東大受験の日々のスタートです。模試の結果は、
前年よりは上がっていますが、やはり最高でもC判定。夏休み頃になると
現役の受験生達も力をつけてきて息子の力不足が浮き彫りになります。
私は息子に様子を聞きました。息子は「東大の試験は物凄いスピードが
要求される。それも正確に物凄い量をこなさなければならない。」
「時間が有れば解けるけど、俺には難しい」と零してきました。
私は、だったらじっくり考えさせてくれる東工大や京大の方が良いんじゃ
ないかと息子に言いました。結局、この年もセンターの結果が8割をやっと
超えた程度だったので、東大は諦め京都大学を受験することになったのです。
それでも日本一難しい大学であることは間違いありません。東大と京大では
受験の傾向が違っていますので大慌てで京大の受験対策をすることになった
のでした。この年も併願校は早稲田大学でした。それから流石に、もう浪人は
出来ないといういことで「滑り止め」を受験することを強く勧めたのですが、
息子は真剣に私学の偏差値の低い学校の受験を考えようとしませんでした。
分かる気がします。現役のときに、わざわざ辞退して難関大学の合格に
拘ったのですから。二浪までして今更考えてもいない大学に通えるかという
気持ちなんでしょう。この頃やっと私は父親として、建築家としての持論を
息子に細かく話すようになりました。
正直、建築を学ぶのなら偏差値は、ほぼほぼ当てにはなりません。恐らく。
私は高卒ですし、そもそも学校で建築学を教わっていませんから、大学での
建築の勉強が「どれくらい有意義」なのか正確に判断できません。
でも企業に就職をして会社員として働きたいという希望ならば、それは有名な
大学で優秀な成績を収めれば有利になると思います。東大や京大、早稲田を
優秀な成績で卒業すれば、まず間違いなく一流企業に就職できます。
でも建築家になりたいのなら、そこからの「進む道」と在学中に得た「知識」で
大きく進路は変わってくると思います。
何処の大学だって建築を学ぶ内容は大差ありません。1級建築士の資格を
取得することが最終目標のような大学では、建築の一部しか触れることが
出来ないと思います。資格が無ければ働けないような環境に就職するのならば、
そういったことに力を入れている大学を選べば良いです。そうなってくると東大や
京大、早稲田大学は的外れな選択となるでしょう。
こういった話をした結果、息子は日本大学の理工学部建築学科に
「センター利用」で出願しました。完全に日東駒専を舐めていましたね。
ろくなリサーチもしないで出願しました。勿論出願は、センター試験前なのですが、
8割を超えた結果に流石に親の私も受かっているだろうと思っていました。
ですが結果は不合格。背筋が伸びた状態で早稲田の受験、京大の受験と
なりましたが、結果この年も全落ち。息子の様子を直視できませんでした。
ですが、三浪に突入したときは今までと違い浪人生活を楽しむような気配すら
感じられました。勉強が楽しくなってきたのでしょう。息子は言っていました。
高校生のときに化学の授業が全く分からなかった。何を言っているんだろうという
くらい、全く理解できなかったと。息子は独学で化学を習得しました。
地味に教科書やチャートを解き、有名で高度な参考書や問題集を解いたのです。
最初は相当に苦しんだようです。でも記念受験では無く、本気で京大を
受けて合格しようとするだけの「力」のようなものを自分でも持っていると感じて
いたのでしょう。
相変わらず模試の結果はC、B判定止まりでしたが、安定していたので
私の眼からも今年は、いけるかもしれないと感じていました。今回は流石に
リサーチも十分して滑り止めには工学院大学の建築学科をセンター利用で受験
しました。今回のセンターの結果は8割を越えましたが、わずかに8.5割を
下回ってしまいました。 なんとか京大の合格最低レベルくらいです。
日大理工建築のセンター利用の合格ボーダーは8.5割です。一般で受けることに
しておいて良かったです。というか、センター利用で合格できる中堅以上の
私立大学は「滑り止め」のような受験校には成り得ないと感じました。
工学院の合格、そして日大の合格は気持ちに、ゆとりが出来、本命の
早稲田、京大の受験に弾みがつきました。この時点で息子は私立大学に
進むつもりは持っていなかったようです。やはり私大は、お金が掛かります。
文句なしの名門であり、学費も抑えられ「リベンジ」も果たせる、三浪の苦労を
吹き飛ばすことの出来る京大の入試こそ自分の大本命だと位置づけていたと
思います。早稲田の受験後の印象では「微妙」だと言っていました。
でも、それまでの感想とは大分違っていました。全く出来なかったという表情では
なかったのを良く覚えています。京大の受験には同行しました。
相当に力んでいました。初日の英語で失敗してしまったようです。完全に
パニックになったと言っていました。それでも去年は結果的に「ゼロ完」だった
数学も「3完」出来たし、本人も手ごたえを感じていたようでした。京大の
試験2日目が早稲田の合格発表でした。私は清水寺にやっと辿り着いた
広場でネットの発表を見ました。息子の受験番号は有りませんでした。
「補欠」にも有りませんでした。物凄い喪失感でした。それでも御本尊様に
手を合わせないで帰る訳にはいかないと、自分を奮い立たせ、
なんとか御本尊様に手を合わせて息子を京大まで迎えに行きました。
会うと疲れきった様子でした。「あんまり出来なかったな」と力なく答えました。
私は息子の頑張りを褒め称え、兎に角「あそこのラーメンを食って早く家に帰ろう」
と、去年も帰る際に立ち寄った祇園のラーメン屋に息子と向かいました。
何ともいえない表情でした。駄目だったというものでもなく、自信に満ちたもの
でもなく。疲れてはいましたが、やり切ったという程でもありませんでした。
まだ国立後期試験が残っていましたが「終わった」という表情だった気がします。
息子にとって「京大受験」が全てだったのです。
京大からの帰り道、息子に「早稲田、残念だったな」と話しかけると、
「えっ?そうなんだ。俺、見てなかったから」と。早稲田の合格発表を自分では
見ていなかったのでした。「まぁ駄目だと思ってたけど」と力なく、はにかんだ
笑顔で言われました。私は泣いてしまいそうでした。
帰りの新幹線に乗車して暫くして私は早稲田の合格発表を「見落とし」ている
かもしれないという気持ちと発表の画面を息子に見せたいという複雑な気持ちが
入り混じった状態でサイトを開きました。
補欠者のページをスクロールするも、やはり番号は有りません。何の気なしに
横方向へスライドさせると番号に続きが有りました。「なんだ?!」となりました。
スマホの画面では、ちゃんとファイルが開けないようでした。
左2列に表示された番号のテキストは大きなサイズで、右1列は、随分と小さな
サイズで表記されていました。これは補欠のまた補欠なんだと思いましたが、
番号順に並んでいるだけで、成績順ではないことに直ぐに気が付きました。
その隠れていた小さな番号の中に息子の受験番号を見つけました。
「おい!これ、お前の番号だよな?」と言うと「えっ?!なんであるの?!」と息子。
私が、ちゃんと見なかったからだと謝りました。一瞬で息子の表情は明るくなり
ました。ですが息子は「補欠合格、何人取るのかな。そもそも補欠合格なんて
出るのかな」と半笑いでした。そうなんです。早稲田は補欠合格が全く出ない年も
有れば、補欠全員合格の年も有ります。数年前から政府の指導で合格者が
定員以上にならないような措置を採るように強く指導されています。
今年は1.1倍以上にならないようにと指導されています。ほぼ定員です。
定員は80名。合格者が140名程度。早稲田を滑り止めにしている東大や東工大、
どうかすれば慶応、横国。息子のように遠いところでは京大などに合格した
受験生が辞退すれば繰り上がる訳です。この時点で息子の補欠の順位も
分かりませんし、かえって心臓に悪いです。国立の後期試験を受けることに
なりました。正直、私としては早稲田が受かっていれば国立の後期試験は
受けさせないつもりでした。しかし結果は不合格でした。
息子も私も心のどこかで繰り上げに成って欲しいと願っていたと思います。
結果を受けて国立大学の後期試験を受けることになりました。
信州大学の工学部建築学科です。後期は受けないでもと言っていましたが、
私は流石に私立大学の滑り止めに行くくらいなら、しっかりと国立大学を受けて
合格して欲しいと言いました。息子は「どこでもいいな」と願書を提出する時期には
言っていましたが、後期で希望が叶いそうな大学は千葉大学と名工大、
それに京都工芸繊維大学、横浜国立大学辺りでしたが、センターの結果に
自信が無く、横国は無理だろうとなれば、対策の立てようがない千葉大学も
受かる気がしなく、「受かりそう」という理由だけで信州大学を選びました。
以前は小論文だったこともあるようですが、ちゃんと「数学」の試験が課される
ことが息子には合っていると思ったようです。
受験日の前日に長野市に入りました。ひとりで新幹線を乗り継いで行きました。
初めての地で親としては不安でしたが、着いた日には善光寺参りまでして、
落ち着いて受験できたようです。試験が終わる頃に合わせて私は家内と一緒に
自動車で長野まで迎えに行きました。少し考えが有ったからです。
息子と駅で待ち合わせました。「どうだった?」と聞くと
「まぁ思ったより難しかったよ」と息子は答えました。
続けて「まぁ受かったと思うけど」と力なく言いました。大きな失敗もしていないので
例年のボーダーは軽く越えていたと判断したのでしょう。
この時点で息子は信州大学に通うんだろうなと完璧に思い込んでいたと思います。
かなりの長文になりましたが、まだまだ話は終わりません。続きは明日に。